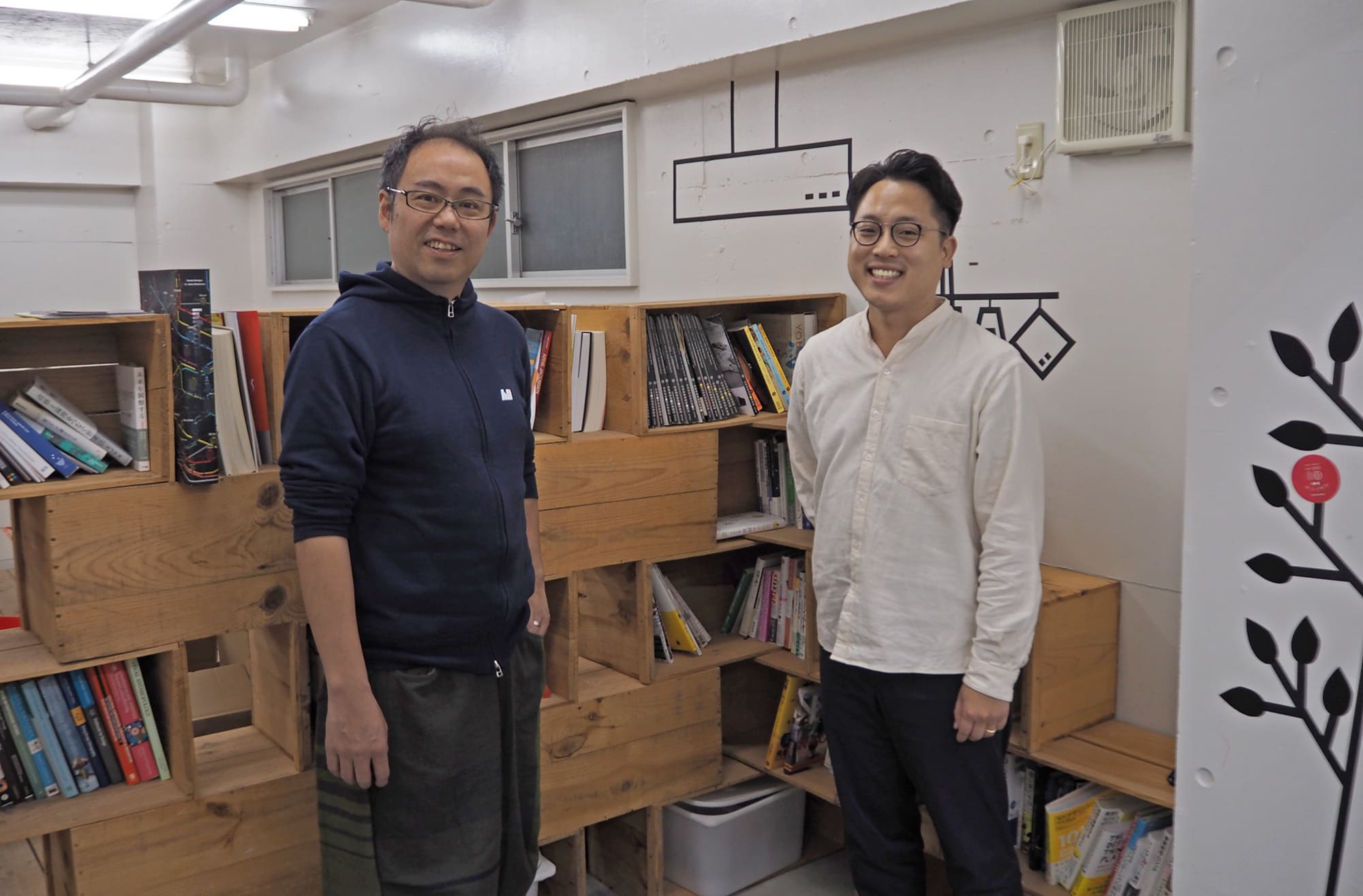ビジネスの世界で「イノベーション」とか「デザイン思考」という言葉をよく聞きます。新しいビジネスを生み出すための方法論と思われがちですが、実はビジネスに限らずあらゆる問題解決に応用できる方法なのです。と言っている私自身、いったいどういうことなのかよくわかってはいないのですが。
RE:PUBLIC(以下、リ・パブリック)共同代表の田村大さんは、博報堂で研究職を勤めていたころからデザイン思考に取り組み、今は企業だけでなく地域のイノベーションに、さらにはまちづくりへと活動の幅を広げています。
なぜいま「まちづくり」なのか、同じように全国で「まち」に取り組んでいるグリーンズ・ビジネスアドバイザーの小野裕之が話を聞きました。
株式会社リ・パブリック共同代表、株式会社UNAラボラトリーズ共同代表。東京大学i.school共同創設者エグゼクティブ・フェロー。九州大学・北陸先端科学技術大学院大学客員教授。2005年、東京大学大学院学際情報学府博士課程単位取得退学。
博報堂イノベーションラボにてグローバル・デザインリサーチのプロジェクト等を開拓・推進した後、独立。人間・社会を中心に置いた視点を活かした、企業や地域のイノベーションに取り組む。
https://re-public.jp
https://greenz.jp/2014/04/07/hiroshi_tamura/
デザイン思考とイノベーション
小野 まず、リ・パブリックってどんな会社なんですか?
田村 イノベーションが起こる環境をつくる会社、すごく縮めていうと「イノベーション建築家」ですね。
小野 田村さんはいくつか会社をやられていて、以前は博報堂にいらしたということですが、どういうキャリアを歩んでこられたんですか?
田村さん 大学を出て就職したのは博報堂だったんですが、それは恥ずかしい話、大学生の頃、ホイチョイ・プロダクションの映画に憧れたんです。『波の数だけ抱きしめて』という映画があって、それが博報堂を舞台にしていて、「なんか広告代理店っていいな」と思って。
小野 (笑)
田村さん まあ半分冗談ですけど半分本当で、それで博報堂に入りました。ただ、広告の仕事はあまり合わなくて、ちょうど1990年代後半のインターネットが盛り上がってきた頃に、今で言うウェブサービスをプロデュースするようになって。それが世の中にどんどん出ていって、一時は浮かれちゃったんです。でも、冷静になってみたら、それはただ未開の地があって誰も開拓していなかったからで、別に自分がすごいわけではなかった。
そこで、きちんと勉強するために20代の終わりに博報堂を休職して東大の情報学環に入りました。そこで、坂村健という師匠、日本発のOS・トロンを発明した天才なんですが、彼に出会って学問のなんたるかを学び、研究者として生きる道を選びました。
小野 そこではどんな研究を?
田村さん 30代前半までは、いわゆるデータサイエンスで人の行動モデルを研究していました。修士論文では博物館の来館者の行動を予測するモデルをつくって、博士課程ではショッピング空間の顧客の行動を予測するモデルをつくっていました。
その中でわりと早い段階で、データだけではわからないことがたくさんあって、人の行動の意味を見つけないとデータのパターンを理解できないことに気がついたんです。それで、観察から意味づけをする方法、人類学や認知科学でいうエスノグラフィックリサーチというんですが、それを使ってコンサルティングをやっているIDEO(米カリフォルニアに本社を置くデザインファーム)に勉強しに行って、その後一緒に仕事をするようになりました。
専門的な話になってきましたが、私なりに解釈すると、データから人の行動の意味をモデル化するのには限界があって、データから見出されたパターンとその意味を照合していかないと、その限界を超えられない。だから、観察から意味を見つける方法としてエスノグラフィーを活用することを考えたのだと思います。
IDEOは2000年代前半から「デザイン思考」という言葉を使っていて、それは大まかに言うとユーザーの行動の意味を知ることからイノベーションの機会を発見し、その機会を活かしたプロダクトやサービスのアイデアを発案することで、新たなビジネスを生み出すものでした。つまり、デザイン思考によって田村さんの研究するデータサイエンスとイノベーションがむすびつくのです。
小野 研究者として東大のi.schoolの開設に関わったりしたんですよね。そこからなぜ会社を起こそうと思ったんですか?
田村さん IDEOと一緒にやるようになった2000年代後半は、ちょうど「これからは論理性がものを言うビジネススクールではなく、創造性に基づくデザインスクールの時代だ」と言われはじめた頃で、それを日本で学ぶ場があればいいと2009年につくったのが、東大のイノベーション教育プログラムi.schoolです。デザイン思考を体系的に学べるプログラムとしては日本で最初のものでした。
そこから3年半、博報堂の社員として企業にイノベーションを起こす研究と実践を重ねながら、東大のスタッフを兼務し、ちょうど半々くらいでやっていました。でも、その間に東日本大震災があって、本当に大事なのは人や社会の希望だと気づいた。企業のイノベーションに人や社会の未来を委ねることでは解決しない、未来をより良い方向に変えていける環境をどうつくっていくかを考えることが大事じゃないか、と思うようになったんです。
それはクライアントビジネスの中だけではできないと思ったので、2013年に独立してリ・パブリックを立ち上げました。
自治体、企業、大学でイノベーションを起こす
小野 リ・パブリックでは具体的にどんなことをしているんですか?
田村さん 一番多いのは、地方行政、特に都道府県レベルとやっているイノベーターを育てる取り組みです。5年前に広島の「イノベーターズハンドレッド」というプロジェクトをスタートし、リ・パブリックとしての標準型ができました。広島にはニッチな領域で、グローバルに影響力を持つ面白い会社がたくさんあって、その中の100社に企業の未来を背負う若手のイノベーターを育てるというものです。県のイノベーション推進チームと一緒にやっています。
田村さん このプロジェクトは、始める前から広島県の人と意見交換をしながら勝手にデータを集めて、広島は今ここが課題でここに一番力を入れるべきだということを県の人に伝えていました。そこから、県の側から「こういうプロジェクトをやりたい」という試案が出てきて、じゃあやりましょうという流れで始まったんです。
このように、地域がもっと創造的になるように環境をリデザインする方法を一緒に考えていくことから始めるのが、行政と協業する際のスタンダードになっています。
企業との仕事も似ていて、一緒に何年もかけてその会社の未来の可能性を育てていくような取り組みが多いです。新しい研究所をつくったり、研究開発のプロセスを構築したり、イノベーションを起こせるような研究開発環境を、外部との関わりも含めて一緒に考えていく感じです。
大学とも仕事をしていますが、その場合でも、産学連携の新しい仕組みを一緒につくっていくような、イノベーションを生み出す環境づくりを協業を通じて実現するという姿勢は同じです。行政・企業・大学とも、やってることはそんなに変わらないですね。
小野 仕事のつくり方というそもそもの部分ですね。そこからの新たな展開というのもあるんですか?
田村さん 最近すこし違うことをやり始めて、それはまちをどうつくっていくかということです。まちづくりといっても今まで不動産デベロッパーがやってきたようなものではなく、人づくりとまちづくりがセットになっているような形のものです。
そのためにMOMENTという都市のデザインについての雑誌を創刊したり、古民家のリノベーションからまちの交流ビジネスを創出するNIPPONIAプロジェクトなんかと一緒に仕事をするようになりました。
イノベーションが起きる環境づくりとは
小野 これまでイノベーションの環境づくりを手掛けてきて、「こういうイノベーションがいいイノベーションだよね」みたいなものってあったりしますか?
田村さん 月並みですが、与えられた「業務」としてやると、イノベーションの楽しさやワクワクが失われてしまうということを問題視しています。なにか新しいことにチャレンジしようっていうのは面白いことだし、楽しめればやってみて失敗してもそれでいいじゃんって思えることが大事だと思うんですよ。そのためには、自分がワクワクしながらやるとか、すごい好きだとか、こういう未来になればいいという願望があるとか、かなり自分のことになってないとだめ。
そう気づいてからは、目を輝かせて「これすごいんです」とか「好きでやってるんです」「こういう社会になったらいいと思ってます」っていう人がいる、ということが前提条件になりました。
小野 もちろん会社の助けは借りるんだけど個人の感覚からであってほしい、ということですよね。でもそれですんなりいくものですか?
田村さん いかないですね。会社のビジネスとしてどうなのかって話は常に悩みのポイントです。でも、最終的に会社のビジネスになればいいのであって、それよりも「本当に自分がやりたいか」のほうが大事だってことはずっと言い続けてます。
残念なことに、大企業の人たちは「自分がこれをやりたい」ってことを見つけるのがだいぶ下手なんです。だから個人の感覚からイノベーションを起こすことが難しい。それに加えて、諦めも出てきちゃうんです。最初から。「アイデアがあるならやればいい」と言っても「できる自信がない」と。会社の中で、あつれきを起こしてまでやりたいことがないからなんでしょうね。
小野 そんなものですか。
田村さん 大きな会社に居続けると、仕事に対するオーナーシップが徐々に蝕まれていってしまうんでしょうね。自分の分担の仕事はきちんとやるんですが、仕事全体へのオーナーシップがないので自分がやったことに手応えを感じられない。それがますます仕事に対するオーナーシップをすり減らす悪循環。
自分がした仕事に対する評価も自分の手応えではなく、上司や経営者の主観で決まる。そうすると、「できる」という自信そのものが失われていくんです。
小野 そういう人たちがイノベーションを起こせるような環境はどうやってつくるんですか?
田村さん 2018年にスタートした熊本イノベーションスクール「Project 180」はそんなプロジェクトです。地元の若手経営者と、東京や関西の大企業に勤めているような人たちを組み合わせて3人一組でチームをつくって、メンターのアドバイスを受けながら新しい事業をつくってもらいます。
意欲あるオーナー企業って意思決定が早いので、話がまとまったらそれこそ1ヶ月くらいでプロダクトリリースできたりしちゃうんですよ。大企業の人にとってはそれが新鮮で、「これだったら自分も色々できるかも」って自信を持つきっかけになる。そういう成功体験をしてもらうことが大事だと思うんです。
まちの問題を解けば世界の問題が解ける
小野 「まち」に向かうようになったきっかけは何だったんですか?
田村さん ひとつは「イノベーションって限られた人がやるもんだっけ?」という思いです。イノベーションを起こせる人と起こせない人がいて、起こせない人は成果を享受するだけだと、送り手と受け手がいる今までの一方通行の構造のままですよね。だから、「できる人とできない人がいる」という考え方自体をなんとかしたいと思ったんです。
そこで、だれでもイノベーションに参画できる社会をデザインしようと考えた時に、そのような場づくりができるのはと考えたら、それがまちをつくることだと思ったんです。
小野 なるほど。
田村さん もうひとつは、まちがいちばん多相性があるから。僕は日本って面白いと思うんですが、それは今の日本がかなり病んでいるからなんです。僕の身の回りにいる人たちで、大企業に勤めてる人も含めて病んでる人が結構多い。でも、この人たちが変わったら社会がめちゃくちゃ面白くなるという期待感もあるんです。そこに可能性があると感じていて。
多相性のあるまちに取り組むことで、今まで見えていなかった回路がつながっていったらそこが変わっていくんじゃないか、熊本の事例みたいなことが次々起こってくるだろうと思うんです。
小野 福岡で新しい事業をはじめたことも関係してますか?
田村さん そうですね。2014年に福岡に移ったんですが、不動産が安いとか、初期投資が小さく済むので、自分で事業をやると面白いかもと思い始めたんです。それで、色々アイデアを考えてきた人たちに、少しお金出すから会社つくろうよって言って、自転車やツーリズムの会社をつくりました。
なぜツーリズムかというと、大都市や都道府県レベルでは建設や農業といった業種ごとでイノベーションを考えることができるけれど、市町村レベルになると地場の産業の規模が小さくて、特定業種の中で発展性ある新規事業をオーガナイズするのは難しいと思ったんです。
じゃあ、いろんな業種を横断してそれをまとめるようなプラットフォームは何か考えたら、ツーリズムだった。まちを考えるならツーリズムはやったほうがいいって話になって、うなぎの寝床の白水くんと話して、UNAラボラトリーズという文化ツーリズムの会社をつくりました。
小野 ほかの地域でも具体的にまちをつくる取り組みをしているんですか?
田村さん 九州のある都市を世界の循環経済の中心になるようなまちにしようという取り組みを始めています。もともと広大な土地に工業団地をつくる計画があったんですが、それだと多少の雇用の積み増しにはなっても、持続的な経済文化の発展にはつながらない。それでローカルとグローバルをつなぐ新しい循環経済の都市モデルをつくろうと、ナカダイ、オープンAなどと一緒にやりはじめたところです。
小野 田村さんは、難しい問題を解きたい方なんですね。
田村さん そうですね。難しい問題のほうが自分のモチベーションが上がるのはそうかもしれない。大学院の指導教官の坂村健に「研究っていうのはどんな小さな領域でもいいから世界ナンバー1になることだ、それ以外は研究じゃない」と言われたことがあって、それから世界で誰もやったことないことをやるというのが自分の行動原理になっている部分はあります。
だから誰も解いたことがない問題を解きたいし、それでより多くの人にいい影響を与えたい気持ちはあります。
小野 ぼくがまちに行き着いたのは、社会の問題を解こうとしている社会起業家や企業内でイノベーションを起こそうとしている人がいた時に、その問題だけを解こうとしても解けないことに気づいたからなんです。
個別で起こっている問題には別の原因があって、そっちに取り組まないと問題は解決しない。その時に、まちという単位で考えると問題解決のモデルケースづくりがしやすいと思ったんです。国全体では変わらないこともまちというレベルだと変えられることが意外とあって、そこから問題解決の方法が導き出せる。
田村さん 僕が最近注目しているのは、長崎県にある東彼杵(ひがしそのぎ)という人口8,000人くらいの小さな町の展開です。このまちのセブンイレブンのフランチャイズオーナーをやっている若者が、ちょっと面白いことをやろうと思って古い米倉庫を借りて、セルフリノベーションして、独立系の小さなお店が集まるモールをつくったんです。
最初は知り合いのネットワークを使ってちょっとおしゃれな感じのお店を入れていったのが、1年2年経つうちにまわりにも波及していって、20軒も新しいお店ができたらしい。そうすると外から人もやってくるから、行政も本腰入れてまちづくりをやろうって言い始めて、みんながやる気になってそれがつながってまちがどんどん変わっていく。
これを見て思ったのが、まちづくりってこういうふうにやる気の連鎖を起こさせる仕組みなんだなって。やる気の連鎖をどうやってデザインしていくかっていうのが、これから僕らが新しい形でのデベロッパービジネスをやっていくときの一つのポイントかなと思っています。
まちと意味のデザインがあわさって生まれるイノベーション
小野 いま下北沢で小さいまちをつくる取り組みをしているんですが、僕がやりたいのは「店」の可能性を探求することなんです。日本では、欧米的な家を行き来しあう文化よりは、半パブリックな存在である「店」が糊付け役になる方が可能性があるなと思っていて。だから、同じ店が好きで通ってる、ということがコミュニティデザインの起点になるのではないかと。
でも、自分で店やってみてすごい大変だともわかったので、そこの折り合いをどうつけるか、もうちょっとスマートな方法はないか悩んでるところです。
田村さん 丹波篠山に丸山集落という12軒しかない限界集落があって、そこに宿があるんです。30代くらいの接客全般を受け持つ女将がいて、その人だけがいわゆる社員で、それ以外の朝ごはんをつくるとか、掃除をするとか、送迎をするのは地元の人たちなんです。集落のおじちゃんとかおばちゃんが、生活の一部としてやってる。
面白いのは、稼働率は3割くらいがいいらしいんですよ。3割でとんとんになるかちょっと利益が出るくらいなので、稼働率を上げれば利益は増えるんですが、4割を超えると集落の人たちは喜ばないんですって。日常の農作業とかもやってるから、疲弊してしまうと。最近は視察も多くて稼働率が上がっているので、キャンセルが出ると集落の人は喜ぶっていう(笑)
田村さん この事例で思うのは、持続する生業のあり方っていうのは必ずしも右肩上がりで成長していくものではなくて、「ちょうどいいバランスを見つける」ことなんだということです。それが彼らにとっては3割の稼働率で、ちょうどいい塩梅を見つけるのって大事なんだと気づかされましたし、これで10年続いているっていうのは意味があるのがよくわかりますね。
小野 そのあたりの意味のデザインって今必要ですよね。
田村さん そう思います。いままではビジネスには無限の資源がある前提でマーケットをどう開拓するかするかみたいな話になりがちでしたが、小野さんがおっしゃるように資源も有限で、その有限性とマーケットのバランスをどう取るのかが大事になってくる。
小野 ユーザーも成熟してきて、「疲弊してまでやらなくていいですよ」みたいに店とユーザーが一緒にそのバランスをつくっていくっていうのも大事ですよね。
田村さん そういう感覚とプロダクトがかけ合わさっていくといいですよね。UNAラボラトリーズで、地域のものづくりと宿泊や体験がセットになったものに取り組んでいるんですが、その時に欲しいものに出会ったとしても、小規模なものづくりなので、1年待ちとかになることもあるんです。その時に、「じゃあ1年後にまた遊びにきます」みたいにできると一番いいなと思いますね。
小野 田村さんの今後の方向としてはそういう地に足がついたというか、ユーザーに近いところにいようという感じですか?
田村さん 今日話して思ったのは、リ・パブリックって研究者集団で頭が良さそうみたいなイメージがあったんじゃないかと。そういう反省です。自分で言うのもなんだけど(笑) 存在自体がどこか上から目線みたいな(笑) これからは上から目線じゃない研究者の集団にしたいなと。人間の不合理さ、近視眼みたいなものも含めて楽しめる社会になるようにしたいですね。
小野 じゃあ、ちょっとバカっぽいリ・パブリックに期待ですね(笑)
田村さんの研究者視点からまちを見てみると、そこに日本や世界が抱える問題を解くヒントが見えるというのが面白いなと思いました。イノベーションやデザイン思考の考え方からすると、まちは多様なユーザーがいる場であり、かつイノベーションを起こす人がたくさんいる可能性の塊だということなのではないでしょうか。
ソーシャルビジネスで社会課題を解こうとしているときには、まちに目を向けてみるとそこに意外と簡単な解法が見つかるのかもしれません。そんな事も含めて、集落丸山や東彼杵に行ってみたいなと思いました。