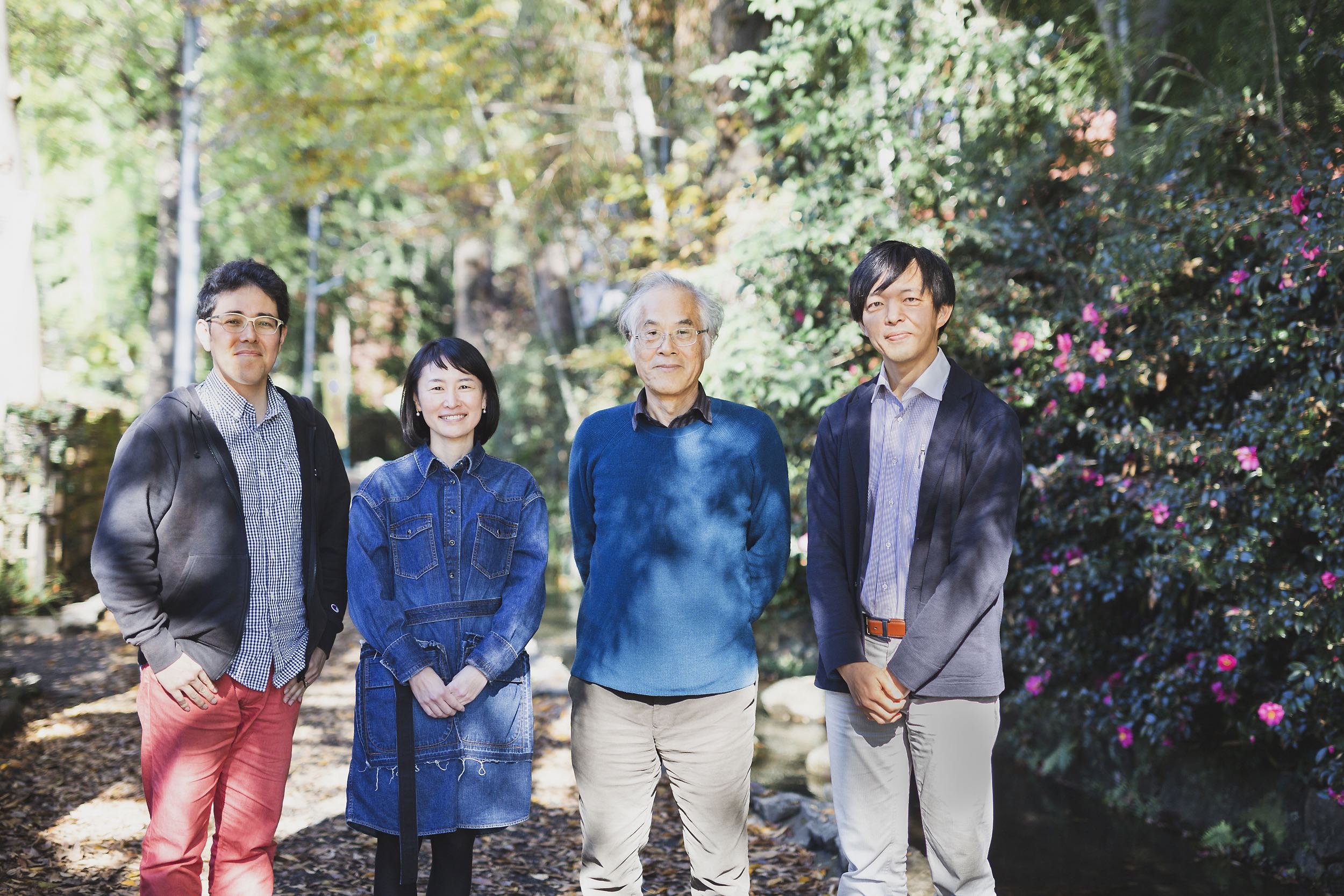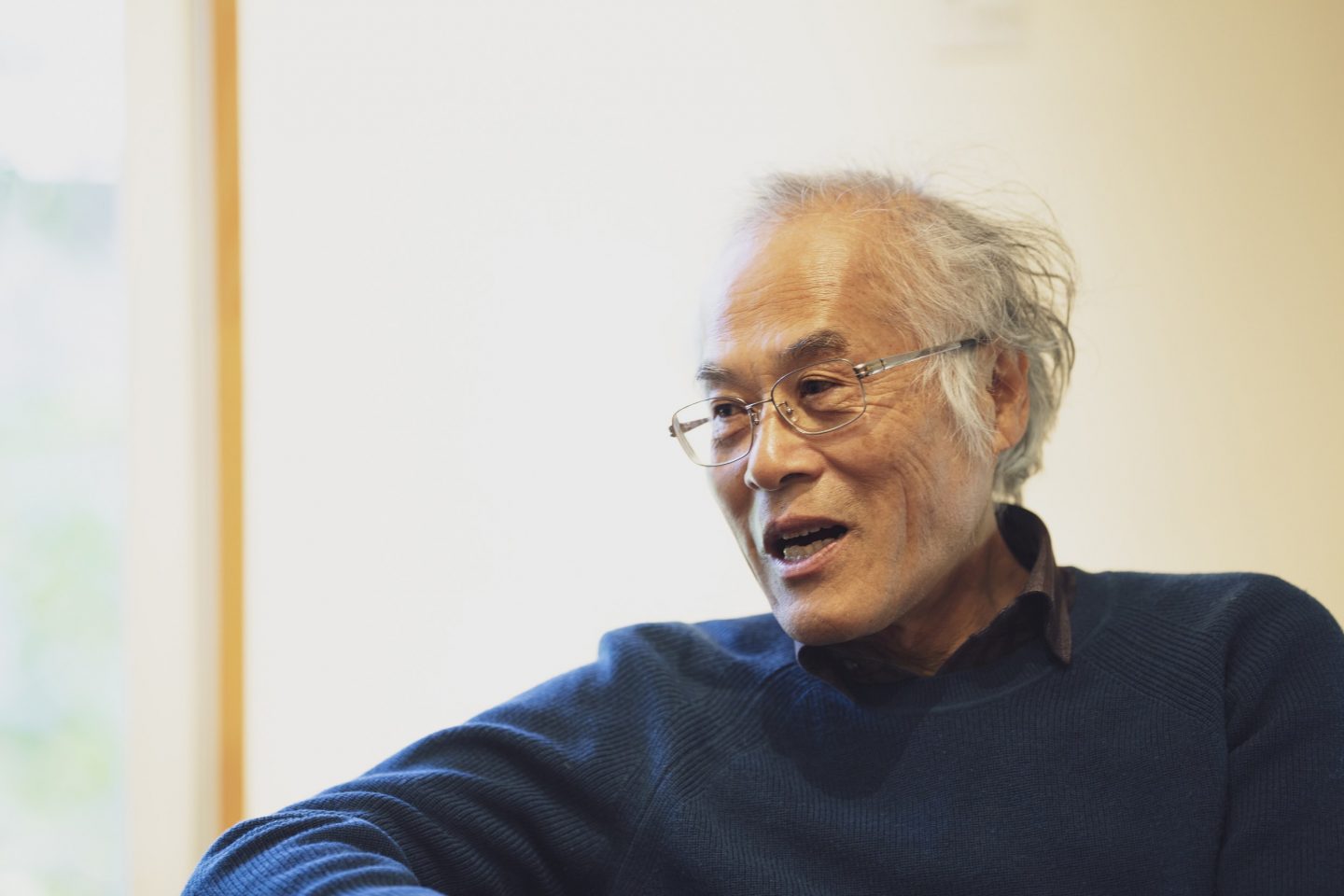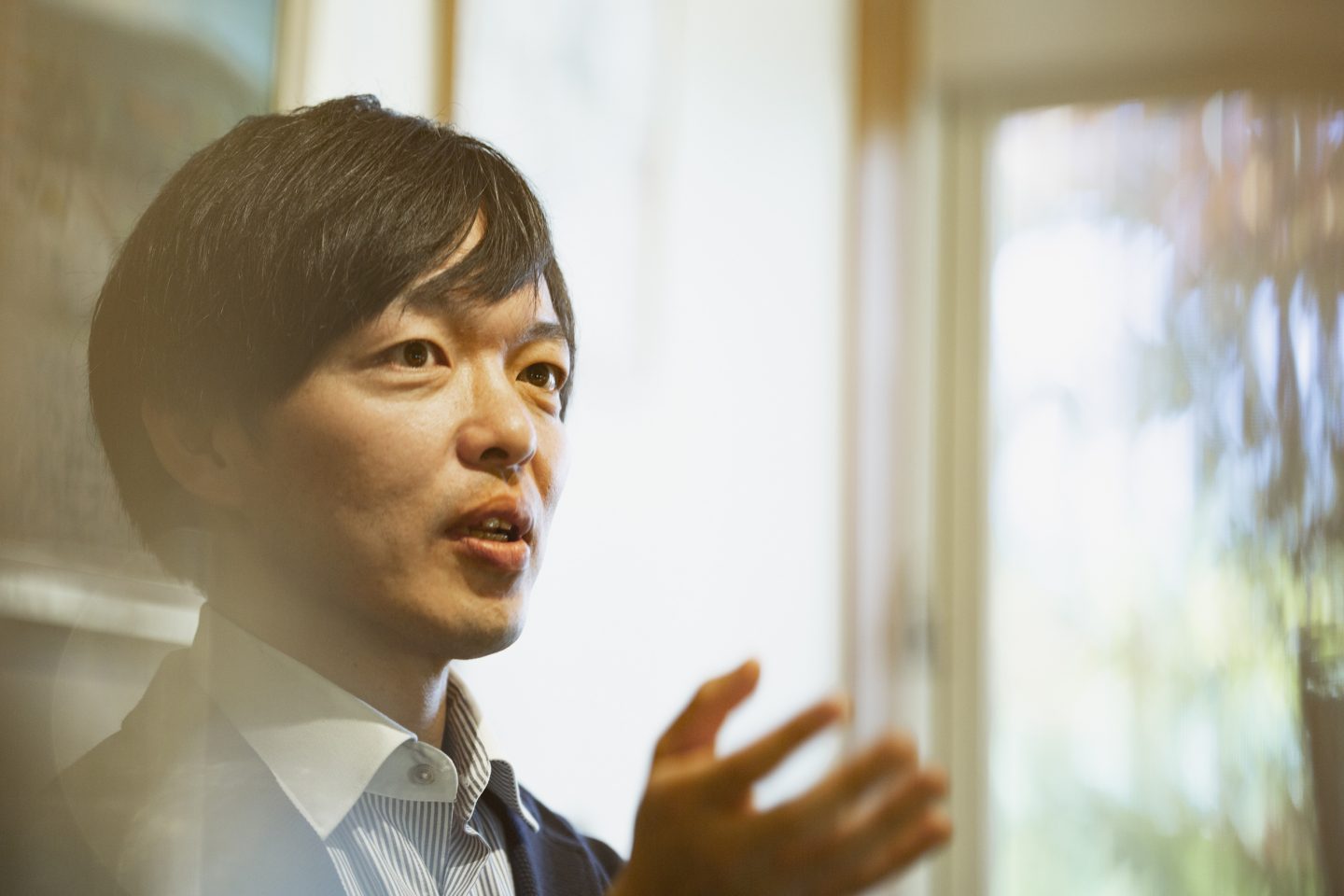日本は国土のうち約70%が森に覆われています。
しかし、戦後に植林された木が活用されず、過密で貧弱になった山林が社会問題となっています。
そこで木を使い、木が循環するまちをつくろうと、竹中工務店とともに始まったのが「キノマチ会議」です。
今回のゲストは、建築家で建築史家でもある藤森照信さん。植物や自然素材を取り入れた建物を、数多く設計しています。
たとえば静岡県掛川市にある美術館「ねむの木こども美術館どんぐり」。
どんぐりをモチーフにしたドーム型の屋根が印象的です。芝棟の屋根には草が生えています。
こちらは、長野県茅野市にある茶室「高過庵」。2本の栗の木の上に建てられ、「世界でもっとも危険な建物トップ10」にも選ばれているとか。
「ちょっと難しい実験を一緒にやってみようという理解のある施主とは、一種の共犯みたいになってねぇ」と笑う藤森さん。そのあふれる冒険心や遊び心を支えるのは、建築史研究者としての思索や、木と向き合う経験に裏打ちされた豊かな知見です。
木のまちづくりへの助言を乞うと、貴重なヒントを山ほど授けてくれました。
1946年生まれ。東京大学名誉教授。専門は近代建築史・都市史。『明治の東京計画』、『日本の近代建築』(上下)、『天下無双の建築学入門』など著書多数。建築作品は、1991年「神長官守矢史料館」、1997年「ニラ・ハウス」(日本芸術大賞)、2001年「熊本県立農業大学校学生寮」(日本建築学会賞)、2013年「オーストリア・ライディング村ゲストハウス」など。
木には2つの使い道がある
今回はgreenz.jp編集長・鈴木菜央と竹中工務店のまちづくり戦略室副部長・高浜洋平さんに加えて、この連載に以前登場したロフトワーク代表取締役兼「飛騨の森でクマは踊る」取締役会長の林千晶さんも、「ぜひ藤森先生のお話を伺いたい!」ということで、急きょ参加されました。
先ほど見たように、藤森さんの建築は自然素材を取り入れたユニークなものばかり。なかには、丸太をそのまま利用したものも。
通常、丸太は構造計算できないという理由で、すぐに切って材にされるそうですが…。
丸太を使うことには躊躇がありましたよ。一応、現代建築の教育を受け、近代建築も知っていますからね。
曲がった丸太の両側面だけ角材と同じにする「太鼓落とし」の材は使っていましたが、初めて枝の跡が残っているような丸太で試みたのは、オーストリアでつくったゲストハウスです。大胆に見えるでしょうけれど、実は相当注意深くやっています。足元から枝分かれしているような木でも実験してみて、これで大丈夫だと。
そもそも構造計算と言っても、木は山によっても切る部位によっても全く違うから。戦後の拡大造林で植えられて多雨で日当たりのいい土地で育った水ぶくれのスギは、普通の倍のビスが必要なほど軟らかい。同じ樹種でも、それほど違うのです。
安全を期すため、木材の硬軟を示すヤング率を測る時に平均的な材ではなく、一番弱い材の一番弱い所の強度を測る人もいると。でも、いちいちヤング率を測るのは現実的ではありません。そこで、藤森さんが勧めるのは、木の使い道を2つに分けて考えることです。
丸太を使う手間と、その管理は、それは大変なものです。自然物である「木」の不安定さから逃れるためには、集成材を使うしかありません。
要するに、表現としての木材と、鉄骨や鉄筋コンクリートと並ぶ産業の建材としての木材があって、この2つは分けたほうがいいのです。そして、両方を組み合わせてやっていかないといけない。
藤森さんは、人間の視覚や触覚に木と感じられる木と、木を原料に使った木の組み合わせについて、「科学技術に服を着せると思えばいい」と表現しました。科学技術を存分に使った外側に、自然をかぶせるということです。
20世紀建築の世界の潮流は、できるだけ骨(構成材)を素直に出して科学技術を表現し、「肉まではいいが皮を付けるのは許さん」という調子でしたが、今は違うと藤森さんは言います。
僕は、できるだけ木については荒々しく使いたいと思っていますが、曲がった木を使うためには鉄やコンクリートの力が絶対必要なのです。基本的に自然のものは弱いけれど味わい深い。一方、科学技術の成果は強いですから。
昔は科学技術が高価だったけれど、今は人手がどうしてもかかる自然が最も高い。だから人に近い所に高価で貴重な自然を、見えない所に安価で大量なものを配する。どれだけ科学技術を入れて安価に抑えるかを常に考えながらやっています。
藤森さんは「規模」についても力説しました。
例えば、木の感じを強く残しつつ強度など安定した性能がある直交集成板(CLT: Cross Laminated Timber)は、オーストリアで開発されてドイツで普及しました。
建設省(1948~2001年)が三層の「Jパネル」などとして日本にも導入しましたが、使い方のスケールがまるで違うというのです。
ドイツの工場には巨大な集成材がザーッと置いてあって、大工さんたちが適当に、豆腐を切るみたいにして使う。表に見せないから、彼らは太ければ太いほどいいという感覚です。
木を美しくみせようとする日本でも、木と感じられない集成材は見えない部分に使えばいい。そうしないと大量には使えないから、森の再生は無理でしょう?
冒頭でも述べた通り、日本は森林率が約70%という世界屈指の森林大国ですが、海外からの安価な輸入材に押され、日本の木は活用しきれていません。
竹中工務店が「キノマチ会議」を始めた背景にも、「木を使わないと山が放置され、台風がきたらすぐ流れて災害が起きるし、そのたびに国のお金で直していたらキリがない。山が適切に保全されるように、都市側ももう少し努力しないと」(高浜さん)という危機感があります。
拡大造林が国策となったのは、戦時中のコンクリートと鉄の不足を補うために大量の木が消費されたため。藤森さんは当時を知る人から、滑走路が立派なヒノキ製の飛行場があったと聞いたそうです。
戦後の政策で木を建築に使うための技術開発が停滞
日本の山を使っていくには「化学の技術が鍵になる」と繰り返す藤森さん。確かに、運搬に関する技術に加えて集成材や防腐剤に関する技術があれば、在庫過剰となった木々を、より効率よく高性能な木材に加工して、より広範な用途で大量に使うことができそうです。
ところが、日本の木材使用には、不幸にも空白期間がある。その一番の原因が、戦後すぐの政策です。空襲や火事、地震や台風による崩壊を受け、防災上の理由で、建築学会や建設省が木造禁止の宣言を出し、産業は絶対に国策に従いますから、学者も木造の研究をやめた。そして木材に関して補助金が出ないから、利活用のための技術開発が止まってしまったのです。
そして、木造のための化学の技術に投資されなかったために、木の腐敗と長年闘ってきた高温多湿の日本は、塗布材なしの木をボルトで締めただけの高層ビルが長持ちするような気候の欧州の国々に、防腐剤や防火剤の開発でも大幅な遅れをとったのでした。ドイツ製の塗布剤は高いけれど質がいいので、たいていの日本の建築家が使っているそうです。
オーストリアで丸太の柱をつくった時、その付け根と屋根の間に水が漏るのが心配で、いろいろ工夫したわけです。そうしたら、現地の建築家や建築会社の人に「日本では木が腐るのか?」って言われて。もう本当にびっくりした。
ヨーロッパのように冬は低温で夏は乾燥し、湿気と温度が同時に高くならない気候だと、バクテリアが繁殖する条件がそろわないから、木の柱も土から少し浮かせておくだけで腐らないわけです。
日本で人気のドイツの高性能塗布材は、毒性があるためにドイツでは規制されてしまったそうです。藤森さんは「より安全で有効な塗布剤を日本で開発できればいいですね」と期待を込めました。
さらに藤森さんは、日本の住宅の更新が早すぎる点を指摘。相続などの都合で、世代交代までのたった20〜30年で終わる家が多いのです。
あるプレハブメーカーの調査では平均19年ですよ。しかも、中古住宅は木造だと評価ゼロ。むしろ取り壊し代でマイナスです。
本来は木造住宅ぐらい増改築向けのものはないのに。法律の規定より柱が多い家は1本や2本抜いたって問題ない。とても楽ですし、ちゃんと中古を生かすべきでしょう。
文献に残っていない、先人たちの広葉樹の使い方
木造文化の停滞が続いていた日本ですが、ようやく潮目が変わりつつあります。
日本の木造建築は、世界最高レベルに洗練されています。建築は宗教建築と住宅に分けられますが、ヨーロッパの宗教建築は全部、石です。木造文化の国でも、永遠に続く願いを込めて石でつくるのです。
その結果、ヨーロッパの「建築家」は木造の民家をつくらない。日本だけですよ、最先端の建築家が木造住宅をつくっているのは。民家の研究だって、日本では建築家がやりますが、ヨーロッパでは民俗学者の仕事です。
極論すれば、建築の勉強は2カ国に行けば十分でしょう。石を学びにイタリアへ、木を学びに日本へ。長い空白期間に木造が生き延びたのは、大工さんや社寺仏閣が継続して木をちゃんと使い続けていたからでしょうね。
ここで林さんが「だから海外からも(飛騨に)たくさん勉強に来るのね」と手を打ちました。間伐で発生する広葉樹の小径木を使った商品開発などを、岐阜県飛騨市で4年前から進めている林さんによると、全国的に廃業する大工が多い中、交通の不便さゆえか、飛騨には木の文化がよく残っているそうです。
森の7〜8割が林野庁の予算が付かない広葉樹ですが、雪の重みを経験して「たわむことも理解している」飛騨の木は、お祭りで200年も使われるような物に使う強い材として重宝されているとか。
「藤森先生は、広葉樹を建築に使われたことはありますか?」という林さんの問いから、話は、クリの木を中心とした日本人と広葉樹の歴史へと進みました。
かつて、日本の普通の住宅は歴史が遡るほど広葉樹のクリを使っていました。関東から東の江戸時代までの植林は、実はクリなのです。メジャーな樹種でした。
ところが、クリは曲がるし、クリタマバチという害虫が繁殖するから、自然界にクリだけの純林はない。だから植林の方法が長年分かりませんでした。神社仏閣に使われた針葉樹と違って、ほとんど文献にも表れませんから。
その謎が、長野の伊那市の長老に聞いて解けました。外見が似ているナラと混植すると、成長が少し遅いクリが、まっすぐ育つのです。
実際、「たねや」の丸太の柱のために木曽のクリ林を探し当てたら、ナラ3〜4本に対してクリ1本の割合で生えていました。ただ、放置された林に道を付けて切り出すのが大変でね。あの丸太の価格は、ほぼ道代ですよ(笑)
クリ以外の広葉樹も話題にのぼりました。藤森さんは、寒い土地でも早く伸びるカラマツの大径木を「虫はつかないし、病気にはならないし、水にも強い」と絶賛。「諏訪湖の船は全部カラマツ製だった」と故郷の思い出を語りました。
アカマツについては、「あの曲がったような曲がらないような、アカマツの曲がりは私すごく好き」と言って、基本的に天井の梁に使っていたこと、その技術は日本の大工にしかないことを教えてくれました。
またシラカバの皮が水分量など絶妙なバランスになる決まった時季にだけ、簡単にペロッとむけることは北欧の人に聞いて知ったそうです。
昔の林業は今でいう鉄と石油の両方を兼ねる最大のエネルギーであり、最大の経済だったから、江戸幕府は当然これを押さえます。
重要樹種のヒノキ・サワラ・アスナロ・ネズコ・コウヤマキを「木曽五木(きそごぼく)」と定め、切ったら首が飛ぶほど厳しく伐採を禁じました。クリは縄文時代の主木で、農民の民家や蔵にも長年使われた木ですが、広葉樹は守られる対象には入りませんでした。
どうやら、民家向けの身近な広葉樹に関する「あまりに現場的な」先人の知恵は、ほぼ記録に残らず、使い続ける人の間で伝承されてきたようです。
木の可能性は未知数。今は試行錯誤の時代
記録が少ない広葉樹はもちろん、空白の半世紀を経て職人が減った針葉樹についても、今では消えた技術や未知の技術がたくさんあります。
しかし建築をめぐる模索は今始まったことではなく、伊勢神宮でも、銅板で柱を包むと銅イオンのはたらきで接触部分の木が腐らないと分かる以前は、柱が腐るたびに人間が入れない信仰エリアに黒いカラスの扮装をした職人たちが入って修理をしていたとのこと。歴史家でもある藤森さんのお話は、絵巻物を眺めるようです。
木を鉄と同じように構造に使うには、さらに技術開発が必要でしょうね。鉄とコンクリートも、今のように安定して自由に使えるまでになるには、実験と失敗と研究を世界中でやり続けているのです。
耐久試験を繰り返して、ようやくある安定した数字が出ているだけで、もともとはいい加減だったのですよ。今でもコンクリートは混ぜて運ぶ日の温度や気候や交通渋滞で強度が変わるから、現場で測定して、ある安全率を確保しているわけです。木の近代化に関しては、今が試行錯誤の時なのでしょう。
greenz.jpの鈴木菜央は、木の可能性に期待を込めて、「建築から産業から個人の生き方や起業まで、木がぐるぐると循環するような社会になって、日本の森がもっと健全になり、私たちの暮らしももっとハッピーなものになっていくだろう」と構想を語りました。
読者の皆さんと進める「キノマチ会議」が、そんな未来への道しるべとなりますように!
(写真: 寺島由里佳)
– INFORMATION –
10/29(火) キノマチ大会議 2024 -流域再生で森とまちをつなげる-

「キノマチ大会議」は、「キノマチプロジェクト」が主催するオンラインカンファレンスです。「木のまち」をつくる全国の仲間をオンラインに集め、知恵を共有し合い、未来のためのアイデアを生み出すイベントです。
5年目となる今年は2024年10月29日(火)に1DAY開催。2つのトークセッション、2つのピッチセッションなど盛りだくさんでお届けします。リアルタイム参加は先着300名に限り無料です。
今年のメインテーマは「流域再生で森とまちをつなげる」。雨が降り、森が潤い、川として流れ、海に注ぎ、また雨となる。人を含めて多くの動植物にとって欠かせない自然の営みが、現代人の近視眼的な振る舞いによって損なわれています。「流域」という単位で私たちの暮らしや経済をとらえ、失われたつながりを再生していくことに、これからの社会のヒントがあります。森とまちをつなげる「流域再生」というあり方を一緒に考えましょう。