
「震災時は、この非常時を生き抜いたという自信のようなものがあふれていたんです」と話すのは、大阪市の北加賀屋に事務所を構える「dot architects」の家成俊勝さん。
「人ってこんな風にしても生きていけるんや」という震災時のリアルな体験は、家成さんが手掛ける建築の確固たる地盤となっているといいます。

1974年神戸市灘区生まれ。20歳のとき灘区にあった自宅で被災。建物は全壊判定が出るほどの被害に遭う。関西大学法学部法律科卒業後、大阪工業技術専門学校夜間部に入学。専門学校在学中より設計活動を開始する。2004年、赤代武志氏と共に「dot architects」を共同設立。2013年の瀬戸内国際芸術祭では「誰もが家を建てられる」をコンセプトに、材料費わずか300万円でコミュニティスペース「Umaki camp」を設計・建設。京都造形芸術大学 空間演出デザイン学科特任准教授。大阪工業技術専門学校建築学科Ⅱ部非常勤講師。
”建築”との出会いは、文化のるつぼ三宮で
高校生の頃から工務店でアルバイトし、土木作業や建築作業に触れてきた家成さんですが、”建築家”になる一番最初のきっかけは、就職が決まらないまま大学を卒業し、三宮のバーで飲んでいたときの会話でした。
バーテンさんが「家成、建築って知ってるか?」って聞くんですよ。「知ってますよ。鉄筋工やってたんで」と答えたら「違う違う。こういう世界があるんや」と言って見せてくれたのが『Anywhere』(NTT出版)という本なんです。
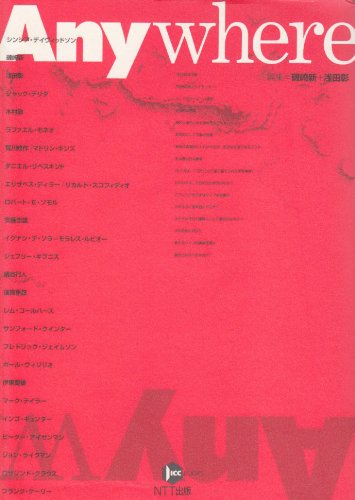
『Anywhere―空間の諸問題 Anyシリーズ』
1991年から10年間にわたって、哲学と建築を議論する国際会議「Any会議」が世界の各地で毎年開かれていました。
メンバーは戦後の日本を代表する建築界の重鎮、磯崎新氏やオランダ出身の世界的建築家レム・コールハース、美術評論家の浅田彰氏など。建築史上に残る貴重な会議の記録をアーカイブした本を、家成さんは手渡されたのです。
読んだら1行もわかんなかったんですよ(笑)
でも、建築ってこんな世界があるんやって思って。現場で必死につくることとか穴を掘るとか、そういうのが好きだったし、それが建築だと思ってたんです。
一方で思想的で哲学的な世界観と建築がつながっているんだっていうのに感動して、この奥行きを体験したいなって思ったんですよね。
その後バーテンダーのアルバイトをしながら、建築の専門学校に通い、知人のバーやクラブの内装設計を次々と任されるようになった家成さん。数年間はこうして活動をしてきましたが、やはり建築のメインストリームを知るべく宮本佳明建築事務所の門を叩きました。
宮本佳明さんは、阪神・淡路大震災で被害を受けて全壊判定を請けた木造の長屋を、重量鉄骨によって補強しアトリエに転用した「ゼンカイハウス」というすごいプロジェクトを手掛けた方なんです。
そのすごさに感動して、宮本さんのもとで半年間勉強させてもらいました。

ゼンカイハウス(宮本佳明建築設計事務所ウェブサイトより)
その後すぐ、友人の赤代武志さんとともに2004年、dot architectsを設立。これまでの建築の流れをふまえつつも、既存の常識にとらわれない自由な発想で活動を続けています。
震災前夜は鳴きやまない犬を撫でていた
家成さんが阪神・淡路大震災で被災したのは神戸市灘区。おばあちゃんの代からずっと住んでいた擬洋風建築のレトロな木造家屋に、家族5人で暮らしていました。
家成さんは今でこそ建築家ですが、当時は法律を学ぶ大学1年生。成人式を2日前に終え、学年末のテストを明日に控えた夜半遅く。飼っていた犬が鳴きやまないため、ひとしきり撫でてなだめてからベッドに入ると、しばらくして「ドーン」と突き上げるような衝撃に目を覚ましたそう。
家の被害はひどく、瓦は落ち、土壁は剥がれ、基礎はゆがみ、ありとあらゆる食器が壊れるありさま。家屋の倒壊こそまぬがれたものの、後に全壊判定を受けたほどの被害でした。
しばらくしてテレビが映し出す被害の様子を見て、友人の安否が気になった家成さんは、原付バイクでまちへと出ました。
うちは灘区でも山手だったので、一見いつもと変わらない風景でした。でも、バス通りに出ると信号は全部止まってて、近所のおっちゃんが五叉路の真ん中で手信号で車をさばいてたんです。うわぁ、すごい人がいるなと思って。
阪急六甲駅の高架下をくぐったあたりから、家がぺしゃんこになったり、心臓マッサージをする人がいたり、と様相が一変しましたね。

「既存の交通ルールを守っていたのでは、にっちもさっちもいかないような状態」というくらい、まちなかは混沌としていたそう。
「友人はおばあちゃんを助けた後にデパートに侵入して、売り物にならないから、と商品を盗んだりもしていました」と振り返る家成さん。善と悪の境目がなくなり、法律や社会の決まりが一瞬にして崩壊した姿を目の当たりにもしました。
友人の無事を確認し、家に戻った家成さんを待っていたのは、たくさんの「生きるためにするべきこと」。
指定暴力団の本部で配給されていたパンをもらいに行ったり、近くのお寺の井戸に水があると聞けば分けてもらいに行ったり。はたまた、プロパンガスを使う家にお願いしてお風呂を借りることもありました。
家は壊れたけれど、代わりに家成さんが手にしたのは”生きる”ためのしたたかさと、人と人が智恵と心を分かち合う絆でした。しかし、このしたたかさは、まちが日常を少しずつ取り戻していくのと同時に薄らいでいったそうです。
震災から3、4ヵ月して、まちが少しずつ元通りに戻っていくのは、良いことなんですけど、心のどこかで淋しくもあったんですよ。
非常時下はヤクザも市民も、みんなで助け合って、どうやったら生活していけるのかということに智恵とアイデアを持ち寄って、自分たちで考えてつくっていた空間があったと思うんです。
でも交通機関やライフラインなど、既存のインフラが復旧しはじめると、また自分たちで考えるということがなくなってきて、生きるということを他人任せにしてる、普通の生活に戻っちゃったなって。
それでは、震災から20年を経た今の神戸を、家成さんはどう見ているのでしょうか?
震災のときに、あんなアグレッシブな状況を生き抜いてきた人たちが集まっているのに、ファッションや文化がコンサバティブなのは、ちょっと意外なんですよね。
物心ともに甚大な被害に見舞われて厳しい状況におかれるなか、被災した人々の間には「こんなんなってるから、どうしようもないやん」と現状をポジティブに受け入れ「で、何やる?」と前を向く気風があったのではないかと家成さんは言います。
そんな「底抜けのポジティブさ」を手に入れようというメッセージが、家成さんの建築のバックボーンになっているのです。
すべての建築のベースには震災がある
阪神・淡路大震災での強烈な体験は、家成さんが手掛けるすべての建築のベース。家成さんは、建築家なら誰もが喜ぶような億単位の設計案件では、「震災で感じた切実さがないからいまいち萌えない」という、建築界の素敵な異端児なのです。
いわゆる建築業界の手法は、スタイロフォームという発泡スチロールで外観をつくり、その中にプランを入れていくんです。
でも「このプランって本当に住む人のためになってるのかな?」と思うんですよ。業界の中で新しいことをするともてはやされますが、それでは住む人も、家をつくる現場の人も疎外されている。
建築家も、住む人も、つくり手も、住まいづくりに関して、すべての人が分断状態にある現代社会。家成さんらが2011年に手掛けた住宅物件「NO.00(ナンバーゼロゼロ)」は、こうした現代社会へのアンチテーゼとしても受け取れます。

兵庫県西宮市にある住宅「NO.00(ナンバーゼロゼロ)」 (c)Takumi Ota

「自分ならどんな家に住みたいか」を考えてもらい、模型を自由につくりかえてもらったそう(c)dot architects
建築の世界はピラミッド構造になっていて、建築家がトップにいて、その人が一人で考えたことを、施主は受け身の存在として「住みなさい」となっている。
この従来の建築のあり方は、震災で経験した社会のあり方と全然違うんですよね。震災のときは、被災した住民同士が助け合って生活を一緒につくり上げた”水平のネットワーク”があった。
震災の時に経験した”水平のネットワーク”を、家成さんらは建築に応用。当時3人で事務所を運営していたので、3人がそれぞれプラン・ディテール・模型を担当し、並列的にプロジェクトを進行させる「超並列設計プロセス」というコンセプトをもとにNO.00を設計しました。
NO.00の竣工の前に、この住宅模型を自由に改変していくワークショップも行いました。20人くらいの学生、社会人、子どもたちに来てもらって1個の模型をどんどん改造してもらったそう。
すると、一人の頭では想像もつかない、お城のようなものができあがってきたのです。
あなたも、私も。誰もが建てられる家
また、昨年度はアートトリエンナーレ「瀬戸内国際芸術祭2013」に参加し、300万円というリーズナブルな材料費でコミュニティスペース「Umakicamp」を制作。小豆島を訪れた観光客と地元の人が交流できる、まちの縁側のような空間を生み出しました。
当初は地元住民の方と一緒に建てようと思っていた家成さんたちでしたが、小豆島では他のアートプロジェクトもたくさんありました。それらに関わることで住民の方が忙しくしていたのを見て、「無理しないで下さい」と伝え、ほぼdot architectsのメンバーだけで建てたそうです。
当初はどうなるかなと思いましたが、建物の基礎ができたくらいから近所の人が自然と遊びにきてくれたんですよ。
敷地が広かったので、かたわらでバーベキューをしたり、子どもが建材の木端で遊んだり。建築行為そのものにかかわらなくても、場所にまつわる人と人とのかかわり方とか、場所とのかかわり方で、良い空間ってうまれるんだなって感じました。

Umakicampは穴のあいたコンクリート製の円柱の基礎に、”ほったて柱”をさしていくシンプルな工法でつくられます。工法には「新しすぎてまだ名前がない」そう。構造設計は満田衛資さんにお願いしました。(c)Yoshiro Masuda

Umakicamp建設中から地域住民の方が野菜や植物を植えたり、場所を自分たちのものとして捉えて、使いはじめてくれたそう(c)dot architects
制作費を300万円に抑えた意図は、単に低価格を目指すことではありませんでした。家成さんがUmakicampで伝えたかったのは、家づくりをハウスメーカーにも、在来構法にも明け渡してしまわない、たくましさと智恵をみんなが持ってるはずだというメッセージ。
家を建てるときの選択肢として、一つは大工に建ててもらう家。もう一つはハウスメーカーの家があります。それはすごく効率良く建てられるかわりに、大規模な生産体制や機械が必要になる。
両方とも肯定した上で、僕らが家を建てるときに、前者ほどの技も、後者ほどの資金も身につける時間がないとする。それでも自分たちで“ものをつくる”ということを手放さずに、協力しあえば家だってつくれるよ、ということを示したかったんです。
Umakicampは建物の中にキッチンとラジオ局を併設し、なんとヤギまで飼ってしまうというユニークな空間でした。
メディアも自分でつくれるし、料理もつくれるし、動物の面倒も見る。その全部を受け身じゃなくて、いろんな人たちと恊働しながら、自分たちで家やルールや仕組みをつくっていけるんだっていうのをやりたかったんですよね。
震災を経験しないとそういうことは考えつかなかったと思います。
ポジティブに問題解決できる心と身体を手に入れる
家成さんは、現在dot architectsとして、金沢市にある「21世紀美術館」で開催中の「ジャパン・アーキテクツ3.11以後の建築」に参加。1月4日から金沢市内の中学生が展示する”市民ギャラリー”の会場構成を担当することになりました。
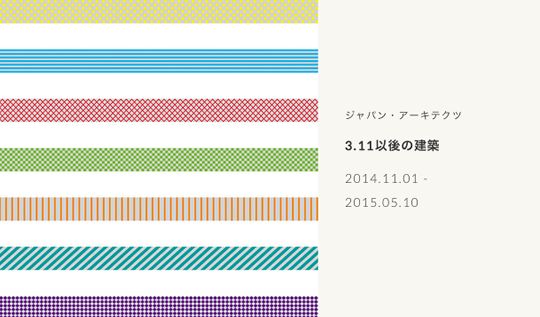
ジャパン・アーキテクツ 3.11以後の建築
生徒の作品を展示する空間をつくるため、まずはどんな作品づくりをしているのだろう、と市内の中学校を回ったときのこと。
「指導要領の改訂で、美術の授業時間が削られ、屋外に出て写生すらできない」など、手を動かしてものをつくったり、学校と地域社会を結ぶ接点が減っていることがわかったそうです。
美術の授業では、準備と後片付けに時間がかかります。授業時間が削られた分は、教材をキット化して対応することになります。ところがキットを使うと、どうしても表層のデザインを考えることになりがちなんですね。
それよりも「自分たちで方法を考えながらつくり上げられる課題を提案したい」と思い、落ちている石や枝など、なんでも利用して「石を吊るす」ということを考えました。
災害時には助け合いや、復興など、さまざまな問題に対応する方法が問われますからね。
このプロジェクトにおける家成さんの目標は、「災害時でもポジティブに問題を解決できる心と身体を手に入れること」。そこには新世代の建築家としての提案が詰まっています。
「災害に備えていますか?」と聞くと「避難袋とか?全く備えてないですね(笑)」と快活に笑う家成さんに、何だか底なしの勇気をもらいました。
必要なのは、いろんな立場の人と恊働して、智恵を出し合って動ける強い身体と柔軟な心。家成さんのようなポジティブな心の持ち方を、私たちもぜひ備えておきたいと思いました。
(写真: Shibata Yosuke)
