「これは、わたしにとってはけっこう快適な状態」
そう語る女性の部屋は、服やビニール袋、本などで埋め尽くされ、ほとんど足の踏み場もない。
東海テレビが2019年につくった公共CM『見えない障害と生きる。』のいち場面。女性は、片付けられない。「こういうことが苦手だから、手伝ってほしい」とパートナーに伝えたところ、「言い訳だ」と理解してもらえず、離婚した。女性は、「発達障害」だった。
「発達障害」とは、「自閉症スペクトラム障害(ASD)」、「注意欠如・多動性障害(ADHD)」、「学習障害(LD)」に代表される、生まれつきみられる脳の働き方の違いにより、行動面や情緒面に特徴がある状態のこと。
僕の身近にも当事者がいる。頭ではその特性について知っていても、ともにすごすなかで戸惑ったり、すれ違ったりしてしまうことがある。冒頭で紹介したパートナーを「冷たい人だ」と言える自信は、僕にはない。きっとCMの女性が経験したようなすれちがいは、あちこちの家族で起きているんだろう。
障害の当事者が、自らの障害を受け止める「障害受容」という言葉があるが、家族にも「障害受容」があるのだと思う。自分や大切な人が発達障害だとわかったとき、家族として、障害をどう受け止めていくことができるんだろう?
そんな問いを携えて話を聞いたのが、遠藤光太(えんどう・こうた)さんだ。光太さんは、発達障害(ADHD、ASD)の当事者。現在は奥さん、娘さん(9歳)、息子さん(1歳)と4人で暮らしている(年齢は2023年1月現在)。
光太さんは著書『僕は死なない子育てをする 発達障害と家族の物語』で、23歳で結婚して父となったあと、鬱になり離婚や自殺をしかけたりして発覚した発達障害を、家族で受け止めてきた過程を書いている。
“悩み続けて、いまでも発達障害を克服できていない。
ただ、八年間の苦闘を経て、障害とも家族とも自分なりに関係性を築くことができ、ともに生きていく土台と覚悟ができてきたのだ。”
(引用:『僕は死なない子育てをする: 発達障害と家族の物語 』244頁)
光太さんが家族と築いてきた関係性とは、どのようなものだったのだろう。
フリーライター。執筆分野は、社会的マイノリティ、子育て、福祉、表現、デザイン、地域、学び、コミュニティ、スポーツ、会計など。2児の父。平成元年生まれ。発達障害(ADHD,ASD)の当事者。
「特性を障害化させない」家族
「発達障害(ADHD,ASD)」とひとくちにいっても、その特性は人によって異なる。光太さんの場合は、過集中や感覚過敏、片付けが苦手なこと、疲労への鈍感さなどがあるという。
最近行った家族旅行でも、ちょっとしたトラブルがあったらしい。
光太さん 僕は発達障害の特性もあり、集団行動が苦手なので、初日で疲れちゃって。ホテルに着いた瞬間、子ども二人をお風呂に入れてないのに、寝ちゃったんですよ。妻からしたらすごく自分勝手な行動で、怒ってもいい場面でした。
しかし、奥さんは怒らなかった。寝てしまった光太さんを、起きるまでそっとしておいてくれた。
障害には、「医学モデル」と「社会モデル」という捉え方がある。
「医学モデル」では、障害を個人の心や身体の機能に原因があると捉える。それに対し「社会モデル」では、障害は社会(モノ、環境、人的環境など)と個人の特性があいまってつくりだされているものだと捉える。つまり、個人の特性と環境とのあいだに齟齬が生じたとき、「特性が障害化する」と考えるのだ。
遠藤家では、発達障害を光太さん個人に原因があると捉えず、「光太さんの特性と環境とがあいまってつくり出されている」と捉えているのだろう。
たとえば、家族旅行の場面。僕が奥さんの立場なら、「なんで寝てるの! まだ子どももお風呂に入れてないし、ご飯も食べてないのに!」と怒るかもしれない。それは、個人に原因があるとする「医学モデル」的な捉え方が根っこにあるからだ。
けれど、遠藤家ではそうはならなかった。光太さんは一度寝て、その時間は奥さんが子どもの面倒をみる。起きた後はバトンタッチして、光太さんが子どもの面倒をみる。そうやって、お互いに配慮し合いながら、柔軟に対応したのだ。
遠藤さんはこうした関係性を、「特性を障害化させない」という言葉で説明する。
光太さん 家族で、特性が障害化させないように、生活を組み立てているイメージです。特性があることで生じるズレをなくしていく。お互い配慮しあって、妥協できるポイントを探っているんです。
家族のなかでの「合理的な配慮」をつくる
日本では、「障害者差別解消法」や「改正障害者雇用促進法」で、事業者に対して障害のある人への「合理的配慮の提供義務」が課されている。
「合理的配慮」とは、障害のある人が社会のなかで出会う、困りごとや障壁を取り除く調整のこと。つまり「合理的配慮の提供義務」とは、「特性を障害化させないための工夫をしましょうね」ということだ。
家族やパートナー同士の関係には、「合理的配慮の提供義務」はない。むしろ近しい関係だからこそ、相手を責めてしまって、相手は傷つけるわ、自分も凹むわ…ということになりがちだ。
義務がないからこそ、遠藤家では「特性を障害化させない」ための「合理的配慮」を、自分たちでつくってきた。
たとえば役割分担。
光太さん 僕が調子を崩していたときは、妻が働いて、僕が主夫をしていました。子育ても、妻はノリノリで遊ぶのが得意で、僕は弱さに寄り添うのが得意。だから、場合に応じて分担してます。「父親らしさ」とか「母親らしさ」にとらわれないで、 それぞれの特性に合わせて生活してるんです。
また、合意のとり方も工夫している。
光太さん 僕はなんでも言葉で説得したくなってしまうんです。でも、妻は言葉で説明されるのが好きじゃない。
たとえば僕が「食洗機を買いたい」って思ったとき、「食器洗いを時給換算するといくらで、この金額で買えば何年で償却できて…」って、一生懸命プレゼンしたんですよ。でもあとから聞いたら、妻は途中から「いいから買えば?」って思ってたらしい、ってこともありました(笑)
言葉で説得しなければと思ってしまう遠藤さんと、感覚を大事にする奥さん。今ではお互いの特性を理解したコミュニケーションをとっている。
たとえば遠藤さんは、大事な相談をするときには「空気」を大事にするようになった。
光太さん 発達障害の特性もあって、僕はあんまり場の空気を読めないんです。でも、結婚してはじめて「空気って大事なんだな」って気づきました。
家族の空気がわるいときに大事な相談をすると、いい対話にならない。だから大きな買い物をしたいときは、家族の関係性がいいときに「あれ買ってもいいかな?」ってひとこと言えばいいんだって、結婚生活を通して学んでいったんです。
遠藤家では、光太さんの発達障害の特性だけでなく、奥さん、子どもたち、それぞれの特性が「障害化」しないように、合理的に配慮しあう関係をつくっているのだろう。
「特性が障害化する」のは、発達障害に限ったことではない。一人ひとりの身体的な特性(たとえば「朝起きるのが苦手」「気圧の変化によわい」など)や、心の特性(たとえば「暗いニュースを見ると落ち込む」「思い通りにいかないとイライラする」など)といったことも、配慮がなければ家族のなかでズレを生むことがある。
そうならないためにも、それぞれの特性に合わせた「合理的配慮」は、きっとどの家族でも必要だ。
過剰適応、うつ状態、奥さんとの出会い
「特性を障害化させない」ためには、家族それぞれの特性が尊重されるオリジナルな関係性をつくり続けていくことが欠かせない。そのための土台になりそうなのが、後で紹介する「家族の開かれた対話」…なのだが、その前に光太さんと遠藤家の歩みを振り返ってみたい。
1989年に生まれた光太さんは、集団行動やルールに馴染めず、あまり幼稚園や学校にいけない幼少期をすごしていた。
光太さん 今思い返せば、当時から発達障害の特性が出ていました。
だが、当時は現在ほど発達障害のことが知られておらず、親もなんとか学校に通わせなければと焦っていた。光太さんも「親を安心させたい」と、無理して園や学校に通っていたという。
光太さん 小さい頃から、環境に適応するために必死でした。悪い意味で優等生になろうとしていた。「過剰適応」の癖がついてしまっていたんでしょうね。
過剰適応によるストレスが限界を超えたのが、大学3年から4年に上がるころ。就職活動や研究室での活動がうまくいかず、東日本大震災のニュースに触れたことも重なってストレスが溜まり、光太さんは深刻なうつ状態になった。
思い詰めて大学を辞めることも考えたが、親に止められ、半年間休学することに。現在の奥さんと出会ったのは、そんな休学中、共通の友人に誘われて行ったライブでのことだ。
駆け引きが苦手だという光太さんは、出会った日に「動物園行こう!」と、半ば強引に予定を取り付けようとした。奥さんもあまりの押しの強さに「仕方ないから行くか」とあきらめたらしい。
何度か会ううちに意気投合し、付き合い始めた二人は、光太さんが社会人1年目、23歳のときに結婚。すぐに第一子となる娘さんが誕生する。
順風満帆に見える家族の船出。でも、付き合った当初から、二人のあいだで齟齬が生じることもあったらしい。たとえば、出かけているときに当初の予定と違う行程になると、急な変更が得意でない光太さんは混乱してしまい、「もう帰ろう」と言い出すようなことがあった。
光太さん 今だったら、発達障害の「臨機応変な対応が苦手」っていう特性からきてるってわかるんですが、当時はお互いそんな知識はなかった。僕も混乱したし、妻は「なんでだろう?」って不思議に思ってたみたいです。
「普通の家族像」や「理想の父親像」に近づくために、必死だった
新卒で入社した編集プロダクションの仕事は、光太さんにとって楽しいものだった。プロジェクトの進捗管理担当として、編集者やデザイナー、クライアントとやりとりしながらコンテンツをつくる仕事にのめり込んでいった。終電まで仕事をする日も少なくなかった。
一方で、発達障害の特性がある光太さんは、気づかないうちにストレスをためこんでいた。感覚が過敏だから、満員電車の混雑や音がつらい。空気を読むことが苦手だから、コミュニケーションには人一倍気を使う。新入社員に任される電話対応も、臨機応変な対応が苦手な光太さんにとっては大きな負担になる。高揚感の裏で、身体はボロボロになっていった。
子どもと生活することのつらさもあった。綿密に計画を立てることで変化にも対応してきた光太さんだが、子どもという存在は予測がつかない。急に体調がわるくなったり、夜に泣き始めたり…。光太さんにとって娘の存在は、コントロール不可能な「自然」のようなものだった。
満員電車に揺られて会社に行き、緊張しながら働く。家に帰れば娘という自然と対峙する。さらに、保育士だった奥さんが仕事が多忙だったこともあり、夫婦ともに苦しい状況に追い込まれていった。
光太さんは当時を「『普通の家族像』や『理想の父親像』に近づくためにエネルギーを費やしていた」と振り返る。
光太さん 男として、妻や子どもを引っ張っていかなきゃいけないんだと思っていた。一言で言うと、「主人」になりたかったんです。 それが男として普通なんだと思っていた。普通でいられなくなることが、怖くて仕方がなかったんです。
「Toxic masculinity(トクシック・マスキュリニティ)に染まっていた」と、光太さんは当時の状態を説明する。「トキシック・マスキュリニティ」とは、伝統的に「男はこう振る舞うべき」とされる行動規範のうち、負の側面があるとされるもの。いわば「有害な男らしさ」のことだ。
そうした男らしさを大事にした父親の姿を見て育っていたこともあってか、光太さん自身も無意識のうちに、「有害な男らしさ」に染まっていた。
うつ、誤診。退職を決意
ある朝目を覚ますと、光太さんはめまいやだるさを感じた。体温は34.6度。病院に行くと、うつ状態だと診断された。
その後、頭がかち割れるような頭痛や身体のだるさ、吐き気、胃痛、体重の増加など、さまざまな身体症状があらわれるようになる。布団から出れず、なんとか家を出ても途中で電車を降りてしまったり、呆然として終点まで乗り過ごすような日もあった。精神科に通ううち、躁状態とうつ状態をくりかえす「双極性障害」だと診断された。(その後、誤診だったことがわかる)。
光太さんは「なんで自分はこんなにダメなんだ」と、現実を受け止められなかった。しかし、「育休をとれば?」という奥さんの一言をきっかけに会社を休むことに。育休であれば、双極性障害であることを受け入れなくても、休む大義名分が得られるからだ。
休職期間には、「早くなんとかしよう」という焦りから、いろいろな方法を試した。1日2回のランニングを試してみたり、皿洗いを始めたり、フットサルをやってみたり。気分の波を抑える薬や睡眠導入剤、抗うつ剤の量も増えていった。
しかし、なかなか症状はよくならない。情けなさや、家族が離れてしまう不安が募り、「自分はいないほうがいいのではないか」と、毎日考えるようになった。
結局、休職開始から7ヶ月で復職するも、半年後にまた休職。その後、退職を決意する。
光太さんは著書で、当時の思いを綴っている。
“どうすればいいのか皆目わからなかった。素晴らしい勤務先に、体調のことを理解してもらえていた。だからこそ「この会社でやっていけないのなら、週五日フルタイムの会社勤めは無理だ」という諦念が頭をもたげた。あっけなく退職した。”
(引用:『僕は死なない子育てをする』44頁)
別居合意書をつくり、自殺も考えた
仲の良かった夫婦も、離婚を考えるまでに険悪になっていた。奥さんから、「一緒にいられない」と告げられた。
光太さん 確かにそうだよな、と思いました。妻も保育士の仕事が忙しいなか、子どもだけじゃなく僕の面倒までみていた。妻も娘も、妻の実家に帰って暮らした方が絶対幸せになれる。だったらお別れした方がいいよなって、自然に思いました。
光太さんは、「別居合意書」の草稿をつくった。奥さんも内容に合意した。しかし、「うつ状態は必ず良くなる。僕が正常になってから、正式に別居の判断をしよう」と、いったん保留にした。(この、「うつ状態の時に重要な決断をしない」という判断が、その後家族にとっての転機を呼び込むことになる。)
会社を退職し、精神的にも孤立した光太さんは、自殺を考えるようになっていた。終電近くに、踏切の棒に触れながら、1、2時間茫然と立ち尽くす夜もあったという。
光太さん 会社を辞めてからバイトもしましたけど、月に数万しか稼げない。娘は頑張って保育園に行ってるのに、自分は…って、娘とも自分を比べて落ち込むような状態でした。
もう、八方塞がりというか…。仕事も家庭も、「理想の父親」であろうとこれだけ頑張ってきたのに無理なのであれば、なにをやってもダメだろうと。
何かの拍子に、一線を超えてしまってもおかしくなかった。それでも踏みとどまれたのは、自分のために、というより、「家族を自殺遺族にしたくない」という思いだったという。
そんなギリギリの状態から脱するきっかけになったのは、「発達障害」の診断を受けたことだった。
発達障害と発覚。感じたショックと可能性
会社を辞め、人生に絶望していたある日。光太さんは何気なくみていたニュース番組に釘付けになる。発達障害の特集で、その当事者が出演していた。
光太さん 「電話対応が苦手」とか「予定にないことを嫌う」とか。その人の話を聞いて、「これは自分のことだ…」と思ったんです。
番組が終わったあと、発達障害のことを調べてみたら、思い当たる節がありすぎてゾッとして。夢中で調べているうちに、気がついたら朝になっていました。
自分は、発達障害かもしれないー。そう思った光太さんが、思い当たることをメモして主治医のもとを訪れると、何度かの検査ののちに発達障害(ADHD、ASD)だと診断された。双極性障害という診断は、誤診だったのだ。
光太さんはショックを受けた。なにしろ、それまでの2年間、双極性障害に苦労して対処してきたのだ。副作用に苦しみながらも薬を調整し、もどかしい思いで仕事を休んできた。この苦労は、なんだったのかー。
ただ、そんな悲しみと同時に、光太さんは希望も感じていた。「自分が発達障害を受容することは、夫婦関係の修復につながるかもしれない」と。
光太さん それまでの26年間、生きづらさの原因がわからなくて、努力がことごとく空を切っていた。でも、発達障害だとわかって、立ち向かうべき特性が明確になったんです。
先程紹介した「トキシック・マスキュリニティ」も、発達障害との相性がわるかったのかもしれない。光太さんの場合、「過剰適応」と呼ばれるような特性があり、周囲の環境に合わせなければという考えが強く出てしまう。人一倍「普通の家族像」や「理想の父親像」にこだわってしまいやすい心の構造があった。
逆に言えば、発達障害を受容していくことは、「普通の家族像」や「理想の父親像」へのとらわれを、ときほぐすことにもつながるかもしれない。光太さんの目の前に、可能性がひらけてきた。
光太さん 僕は「普通の家族」はつくれなかった。ですが、「普通の家族」っていう抽象的な概念ではなく、「僕と妻と娘の、具体的な関係」をつくっていく役割ならできるかもしれない。そう思うようになったんです。
関係性に目を向ける
発達障害だとわかった光太さんが目を向けたのは、「夫婦の関係性」だった。
光太さん 「カサンドラ症候群」という言葉がありますが、僕たちもまさに夫婦関係に一番悩んでいたんです。もちろん特性への医療的な対処はしつつ、やっぱり一番に取り組むべきは夫婦関係の改善だなと思いました。
「カサンドラ症候群」とは、家族や身近な人に自閉スペクトラム症(ASD)があることで、関係の問題や心身の不調が生じている状態のこと。光太さんと奥さんのあいだでも、発達障害の特性によって関係性の齟齬が生まれてしまっていた。
であれば、関係性を改善していくことで、家族のなかで発達障害の特性が障害化せずにすむようにできるのではないか。冒頭で紹介した「社会モデル」の捉え方だ。
夫婦の関係の改善のために、光太さんと奥さんはいくつもの工夫を始める。
それまでのような言語によるコミュニケーションではなく、非言語のコミュニケーションを重視することにした。たとえば、奥さんの肩が凝っていたらマッサージをしたり、仕事後に化粧を落としてあげたり、奥さんが好きなデザートを買って帰ったり。
また、特性として「言われたことを記憶できない」ということがあったため、口頭で事務連絡をするのではなく、Slackというコミュニケーションツールを使ったり、紙に書いたりして、視覚情報として残しておくようにした。
そうした工夫を、その都度すり合わせていく。一方的に「こうしてほしい」と伝えるのではなく、特性も伝えた上で、どうすると二人にとってストレスなくいられるか、具体的な方法を探っていったのだ。
さらに、関係性を夫婦だけに閉じるのではなく、外に開いていくこともした。当時は1LDKの狭い部屋で、夫婦と娘さんの3人で暮らしており、閉じた関係になっていた。そこで、発達障害の特性を持つパートナーと離婚したという方に、夫婦で会いにいった。
光太さん その結果、「やっぱり別れた方がいい」って妻に思われたらしょうがないって、覚悟して行ったんですよ。
そしたら、妻とその方は「発達障害のパートナーあるある」みたいなトークで盛り上がって。終わったあと、「よくわかんないけど楽しかった〜」って言ってました(笑) そのくらいの時期から、ようやく家族が外の世界とつながってきて、関係性がほぐれていきましたね。
鍵を握る、「家族の開かれた対話」
こうして、だんだんとつくられていったのが、冒頭で紹介したような一人ひとりの特性を障害化させない家族のかたちだ。そんなかたちをつくっていくにあたって、おそらく土台になっているのが、遠藤家ならではの「家族の開かれた対話」の時間である。
遠藤家では、頻繁に家族で話し合う時間をとっている。例えば「ドラム式洗濯機を買うかどうか」といった家族の決めごとを話し合ったり、「明日学校に行きたくない」「最近疲れてる」といったモヤモヤを吐き出したり、「◯◯を頑張ってたのがすごかった」「◯◯をしてくれて助かった」と、感謝や賞賛を伝えたり。
そうした時間を通して、「そんなことを思ってたんだ」とお互いが気づき、家族の一体感が育まれているのだという。
具体的な方法はこうだ。
まず、「話したい」と思った人が声をあげ、話し合う場を持つ。場所はダイニングテーブルであることが多いらしい。
家族が集まると、一人ずつ順番に、その時話したいことを話していき、もう誰も話すことがない、となるまで話し続ける。「言いたいことを言いきる。相手はそれを聴ききる」ことを大事にしているのだ。
だから、時間は決まっておらず、15分ぐらいで終わる時もあれば、1時間ずっと話してるときもある。話した内容は、ノートに記録しておいて、別の家族会議の機会に「そういえば前、こんなこと言ってたね」と参照されることもある。以前は週に一度、開催していたが、最近では誰かが「話したい」と言い出した時に開かれるようになった。
光太さん 家族の関係性が良くなったからだと思うんですよ。以前は定期的にやる必要があったんですけど、今はそこまで必要がなくなったんだと思います。
オープンダイアローグから学べること
遠藤家で行われている対話の時間は、「オープンダイアローグ」に似ている。
「オープンダイアローグ(開かれた対話)」とは、1980年代からフィンランド西ラップランド地方で開発されてきた、精神疾患に対する治療方法。その大きな特徴は、入院や投薬によってではなく、「対話」によって症状に対処しようとすることにある。
患者や家族から連絡をもらってから24時間以内に、医師や看護師が訪問。本人や家族を交えた対話を通して、症状の緩和を目指す。従来の医療のように「医師-患者」といった上下関係はなく、医療チームの話し合いも患者の前で行い、患者の同意なしに治療を進めることはしない。
「対話で疾患に対処できるの?」と思うかもしれないが、これがなんと大きな治療成果をもたらし、世界的に注目されているのだ。
「精神疾患に対する治療方法」と書いたけれど、僕たちが抱える特性は、診断名がつくものばかりではない。学校に行くのが憂鬱だったり、整理整頓されていない環境だとイライラしてしまったり、ひとりの時間がないと息が詰まってしまったり。
そうした特性が、家族のなかで障害化しないようにするために、オープンダイアローグの手法や考え方はヒントになりそうだ。(そもそもオープンダイアローグは、診察室という閉じた環境で行われる家族療法の限界を乗り越えるものとして開発されたというから、家族の対話と親和性が高いのは自然なことかもしれない)
さて、オープンダイアローグには、7つの原則がある。
(1)即時に応じること
必要に応じてただちに応答する。
(2)ソーシャル・ネットワークを引き入れること
クライアント、家族、つながりのある人々を皆、治療ミーティングに招く。
(3)個別で具体的なさまざまなニーズに柔軟に対応すること
その時々のニーズに合わせて、どこででも、何にでも、柔軟に対応する。
(4)責任をもって対応すること
治療チームは必要な支援全体に責任をもって関わる。
(5)心理的な連続性を保証すること
クライアントをよく知っている同じ治療チームが、最初からずっと続けて対応する。
(6)不確かさに耐えること
答えのない不確かな状況に耐える。
(7)<対話>が行われていること
対話を続けることを目的とし、多様な声に耳を傾け続ける。
7つの原則の日本語訳は『オープンダイアローグ』57-58頁、英語表現は Olson, M., Seikkula, J., & Ziedonis, D. (2014) にもとづいたもの。それぞれの意味については、「オープンダイアローグ対話実践のガイドライン」を引用した。
遠藤家の家族会議が、そのままこの原則に当てはめられるわけではないが、かなり重なる部分もありそうだ。ちょっとこじつけかもしれないが、光太さんの話をもとに特徴を挙げてみる。
(1)即時に応じること
誰かが「話したい」と声をあげたら、対話の場を設ける。
(2)ソーシャル・ネットワークを引き入れること
家族のみんながその対話の場にいる。本来のオープンダイアローグでは、家族はもちろん同僚や上司、隣人や友達も呼ばれる。遠藤家ではそこまでの範囲の人は呼んでいないものの、ときにリビングでは妻と友人たちが女子会を開くことがあったり、娘の友達が遊びに来たり、旅行には光太さんの弟を連れて行ったりしている。
(3)個別で具体的なさまざまなニーズに柔軟に対応すること
「この症状が出たら、この薬をつかう」といった一辺倒の対処法ではなくて、そのときどきのニーズに耳を傾け、対応を考え、実践する。たとえば娘さんが「学校に行きたくない」と言ったときには、無理には行かせることはしない。
(4)責任をもって対応すること
「それは学校の問題だから、先生に相談しなよ」といったように課題を他者に投げず、みんなで受け止める。娘さんの登校の例で言えば、保育園や小学校に、光太さんが一緒にいくこともある。園や学校とちょうどよく付き合うことに、家族でともに取り組んでいる。
(5)心理的な連続性を保証すること
お互いをよく知っている家族が、ずっと続けて対応する。
(6)不確かさに耐えること
対話の場を設けるからといって、性急に答えを求めようとせず、自分が正解だと思うことに固執しない。相手が自分と違うことを言っていたら、自分の側が変わる準備を持つ。
(7)<対話>が行われていること
答えを出すことより、対話が行われていること、光太さんの言葉を借りれば「言いきる、聴ききる」ことを大事にしている。自分が抱えていることを言いきるまで対話し、相手はそれを聴ききる。
こうした、家族会議を何度も積み重ねることが、結果的に特性を障害化させない家族のかたちにつながっていったのではないだろうか。
特性がどういうときに障害化するかといえば、一人ひとり固有のものである特性を、「普通はこうだから」といった鋳型にはめこんだときなのだろう。ガチガチに固まった鋳型のうえで、僕たちのやわらかな身体やこころは悲鳴をあげる。
そうではなくて、一人ひとりのニーズに耳を傾けて、特性を尊重し、そのときどきで柔軟に対応していくと、特性はむしろ個性になることもある。
「家族の開かれた対話」は、身体やこころをやさしく受け止める、やわらかい布団のようなものだ。日々をすごす家族という関係のなかに、やわらかい布団のようなコミュニケーションがあれば、僕たちはどんな特性があっても、いくらか心やすらかでいられる。
そんなやわらかい布団のようなコミュニケーションが、遠藤家にはあるんだろう。
発達障害があるから、家族に「弱さ」を持ち込めた
取材前、僕は心のどこかで「発達障害があっても、『普通の家族』としての営みが送れるようになるためには、どうしたらいいのか」と考えていた気がする。
でも、そもそも問いが間違っていたのかもしれない。発達障害は、いや、発達障害に限らず、僕らが一人ひとり持っている特性は、「普通の家族」を営むためになるべくゼロに近づけていくべき「負債」のようなものじゃない。
あらためて、光太さんに聞いてみたいと思った。発達障害が、家族にもたらしたものはあったのだろうか。
光太さん 僕が生きづらさを抱えているからこそ、家族に持ち込めたこともあると思っています。それは、「弱さ」です。
今では僕たち家族は、「弱さがあっていい」という関係性になっている。娘も弱さを表現してくれますし、妻が仕事が大変で辞めたいというときも、家族で対応できた。お互いの「弱さ」を受け止めあえる関係性は、僕の発達障害がひとつのきっかけになって、家族に持ち込まれた気がしています。
「弱さ」を家族に持ち込む。
光太さんの言葉に触れて、僕は『べてるの家の「非」援助論』という本にある、ある部分を思い出していた。
”弱さとは、強さが弱体化したものではない。弱さとは、強さに向かうための一つのプロセスでもない。弱さには弱さとしての意味があり、価値がある。…
「強いこと」「正しいこと」に支配された価値のなかで「人間とは弱いものなのだ」という事実に向き合い、そのなかで「弱さ」のもつ可能性と底力を用いた生き方を選択する。”
(引用:『べてるの家の「非」援助論』196頁)
日本では、「男らしさ」や「父親らしさ」が支配的だった時代があった。それはある意味「強さ」に価値を置く時代で、「弱さ」は乗り越えられるべきものとして、排除されたり、否定されたりしてきた。
いや、過去形じゃない。遠藤さんもそうだったように、その価値観の名残はまだある。僕のまわりを見渡しても、「強さ」を大事にする価値観と、自分が抱える「弱さ」との間で葛藤している人がたくさんいる。
あえて強い言葉を使えば、「強くあらねばならない」という“呪い”を解くことが、現代を生きる僕たちに求められているんじゃないだろうか。
家族が“呪い”の場になれば、それはちょっとした地獄だ。けれど、たとえ会社や学校で「強くあらねば」と迫られても、家族が「弱さには弱さとしての意味があり、価値がある」と認め合える場になれば、それは安全基地になる。
遠藤家は、きっとそんな安全基地になっている。安全基地には、やわらかい布団のような「家族の開かれた対話」がある。そして、光太さんの発達障害の特性が、そんな関係性をつくるきっかけになったんだろう。
発達障害は、愛のない障害ではない
最後に光太さんに、「これは伝えておきたい」ということがあるか聞いてみた。返ってきたのは、「発達障害は、愛のない障害じゃない」という言葉だ。
光太さん 発達障害を持つ人の中には、「愛がない」って思われてしまう人もいるんです。でも、発達障害の定義には、「愛がない」なんて特性は入ってない。
うまく表現できなかったり、愛情の裏返しで意地悪なことをしてしまったりするだけで、ちゃんと愛はある。ズレさえ上手く調整できれば、ちゃんと愛を持った関係性を築けるんです。
発達障害は、愛のない障害じゃない。
そういえば、オープンダイアローグを提唱したヤーコ・セイックラ教授は、オープンダイアローグが治癒をもたらす理由を「愛」という言葉で説明していた。開かれた対話に参加したことで生まれる「愛」の感覚が、人に癒しをもたらすのだと。
なにも、「愛してる」と伝えることだけが、愛のあらわれじゃない。遠藤家のように、弱さも喜びも分かち合う関係性をつくるために、日々試行錯誤していくこと。「家族の開かれた対話」を、うまくいかなくてもいいから取り組んでみること。
その過程自体が、ひとつの愛のあらわれとして、家族の一人ひとりに生きている実感をもたらすことがあるのかもしれない。
取材を終えて
「草相撲」を覚えてるだろうか。オオバコなど、道端に生えてる草同士で引っ張り合い、先にちぎれたほうが負け、という遊びだ。
ときに家族という関係は、草相撲のようになる。
人の特性が交差する場である家族は、それぞれの特性がひっぱりあい、こすれあい、傷つけあう関係になりがちだ。それは「特性が障害化する」と言ってもいい。中島みゆきの歌のように、「縦の糸はあなた、横の糸はわたし…」という関係には、なかなかなれない。
家族のなかで特性を障害化させないために、僕たちにできること。その第一歩は、「関係性に目を向けること」なのかもしれないと、遠藤家の話に触れた今、思う。
なにか問題が生まれたとき、相手に原因があるのではなく、「関係性」にひずみが生まれているのだと捉えて、その関係性をよくすることに目を向けてみるのだ。
そうしたとき、僕ら一人ひとりの特性は、相手や自分を傷つけるものじゃなく、誰かをあたためたり、傷をかばったりするものになり得る。そんな気がしている。
参考文献
井庭 崇, 長井 雅史 著『対話のことば:オープンダイアローグに学ぶ問題解消のための対話の心得』丸善出版,2018
浦河べてるの家 著『べてるの家の「非」援助論 ―そのままでいいと思えるための25章』医学書院,2002
遠藤光太 著『僕は死なない子育てをする: 発達障害と家族の物語』,創元社,2022
斎藤 環 著『オープンダイアローグとは何か』医学書院,2015
ヤーコ・セイックラ,トム・エーリク・アーンキル 著 高木 俊介,岡田 愛 訳『オープンダイアローグ』日本評論社,2016
Olson, M., Seikkula, J., & Ziedonis, D. (2014). The key elements of dialogic practice in Open Dialogue.
The University of Massachusetts Medical School. Worcester, MA. September 2, 2014. Version 1.1.
写真提供:小笠原康太
(編集:佐藤伶)
– INFORMATION –
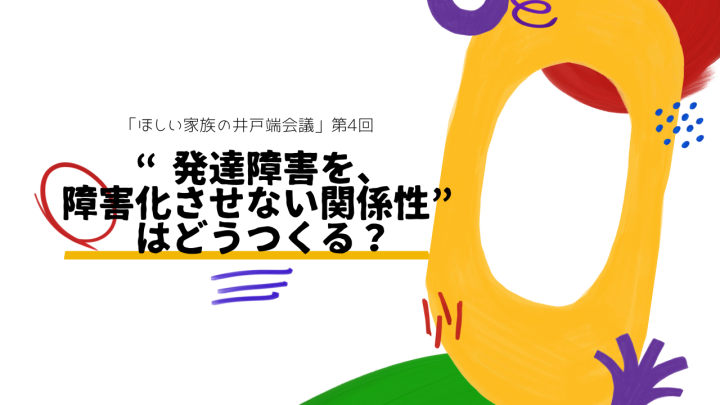
「ほしい家族の井戸端会議」は、本連載に紐づいて「家族」についてゆるゆると対話をする会です。毎回、直近で公開された記事を題材にし、皆さんと「家族」というテーマについてざっくばらんにおしゃべりします。
第4回のテーマは、“発達障害を、障害化させない関係性”はどうつくる?」。ぜひお気軽にお申し込みください!














