始まりがあれば、終わりもある。
ごくごく、当たり前のこと。
でも私たちはどうしても「始まり」ばかりに注目しがち。特にビジネスやプロジェクトの始まりは華々しく脚光を浴びますが、その「終わり」に関しては、注目したり、ポジティブに捉えたりする文化がないように感じます。「あのプロジェクト、知らぬ間に終わってたんだ…」なんて驚いた経験、みなさんにもありませんか?
本日、ハンドメイドブランド「OCICA」は、事業の終了を発表しました。その理由としてSNSで語られていたのは、「みんなの気持ちが前向きな状態で、きちんと終わりを迎えられる」ということ。東日本大震災のあと、石巻市・牧浜(まきのはま)で被災・失業したお母さんたちの仕事として事業化し、約8年間に渡り生産・販売を続けてきた彼らにとって、それは決してネガティブな決断ではないように感じました。
今日は、「OCICA」を運営する「つむぎや」の友廣裕一さんに、事業終了に至ったストーリーと、ビジネスへの向き合い方についてお話を伺いました。始めた当初から「終える」ことを見据え続け、いつでも終えられる状態をキープしてきたと言う友廣さん。それは、事業の目的を全うするために必要なあり方だったそう。
売上や事業規模にばかりに目が行きがちなビジネスの世界の中で、友廣さんの言葉は、「その事業にとって本当に幸せなあり方は?」と、私たちに問いかけてくるようです。自分の関わるビジネスやプロジェクト、人生に思いを馳せながら、「終え方」をめぐる対話を、最後までじっくりとお楽しみください。
いつもお母さんたちの人生とともに。
「OCICA」の歩み
「OCICA」の事業が産声を上げたのは、震災直後のことでした。
そもそものきっかけは、被災地に入って復興支援活動をしていた友廣さんが、牡鹿半島の山中でたくさん目にする「鹿の角」を使って何かつくることができないか、と考え始めたことでした。地域の遊休資源である鹿の角を毎日持ち歩き、出会った人々にアイデアを相談する中で、さまざまなご縁がつながりはじめました。運営メンバー、仕事を必要としていた牡鹿半島・牧浜(まきのはま)のお母さんたち、そしてデザイナーさんと導かれるように出会い、プロジェクトは動き出したのです。
「チャリティグッズではなく、息の長いものを」と、つくり手であるお母さんたちとデザイナーさんでワークショップを重ね、試行錯誤の末、技術面・デザイン面などさまざまな課題をクリア。ハンドメイドブランド「OCICA」として商品の販売を開始したのは、2011年11月のことでした。

輪切りにした鹿の角に、漁網の修復糸を編み込んだその形状は、ドリームキャッチャーにも似ていました。 Photo : Lyie Nitta
以来、お母さんたちの人生に歩調を合わせるように、ゆっくりゆっくりと、ものづくりを続けてきました。2012年には、クラウドファンディングの末、プロジェクトについてまとめた書籍『OCICA—石巻牡鹿半島小さな漁村の物語』を出版。
営業活動はせずとも、牧浜を訪れて生産現場を体感した人々が口コミでその物語を伝えていき、取扱店数も、一時は70〜80店舗にまで拡大しました。オンラインショップのほか、お母さんたち自ら店頭に立った夏フェスなどイベントでの出店も話題になり、「OCICA」は、その背景にあるストーリーとともに、多くの人の知るところとなっていきました。
2015年になる頃からは、牧浜の主産業であり、みなさんの家業でもあった牡蠣養殖が再開したことを受けて、多くのお母さんたちが卒業。それに伴い生産・販売体制を縮小し、当初「つむぎや」メンバーが担っていた生産管理や品質管理などの業務もお母さんたちに委ねました。そのほか、メールの使い方も学んでもらうなどして常駐メンバーを置かない体制にシフトし、“省エネ”モードで運営を続けてきたと言います。
現場のお母さんたち3人でほとんどの業務が回るようになり、規模は小さいながらも持続可能な運営体制を敷いていたように見えていた「OCICA」の事業。このタイミングで終了を迎えた理由は、いったい何だったのでしょうか?
「お母さんたちの笑顔の最大化」を追い求め続けた先に、
ゆるやかに訪れた「そのとき」
ひとことで言うなら、「終わるタイミングが来たから終える」という感じです。
直接的なきっかけは、1年ほど前に3人のお母さんのリーダー的存在だった方が自宅で両親の介護をしなくてはならなくなったことでした。お母さんたちから「終わりを一緒に考えてほしい」と言われたんです。
それで話し合って、1年くらいかけてゆるやかに終わりへと向かうことになりました。
友廣さんは静かに、そのストーリーを語り始めました。
お母さんたちから「終わり」を告げられてから約1年経った今年3月、OCICAを立ち上げた頃から関わった代々の「つむぎや」のメンバーほぼ全員が家族を連れて牧浜を訪問。そのミーティングの席で、正式に「終了」が決定したとのこと。
僕たちとしては、もう1回くらいつくってもらえるかな、と思ってお願いしに行ったんですけど、「家族の状況的に難しくてね」と率直に言ってくれて。じゃあ今回でもう終わりですね、って。なんかみんなで共有できたのがすごく良くて。
良かったね、良いプロジェクトだったね、あんなことあったね、こんなことあったね、って話して、お茶っ子して。「あと1年くらい」って言われてはいたんだけど、僕も決断できない感じで、どうやって終わったらいいのかな、って思ってた。それが、みんなで牧浜に行けたときにそう言ってもらえて、「終われたな」って。
お母さんたちの「終えたい」という言葉を、動揺することなく受け止めた友廣さん。「終われた」という言葉に象徴されるように、OCICAは、常に終わりを見据えたプロジェクトだったと語ります。
そもそもOCICAの事業が「必要なくなったら終える」というのは、2011年に始めたときから、デザイナーも含めたメンバーでずっと共有してきたことで。
震災後の状況の変化の中で、この事業がまったく必要なくなる可能性もあるじゃないですか。かつてのように浜に産業が戻ってきて、お母さんたちもバリバリ仕事できるようになることも想定できましたし。必要なくなって、「じゃあね」って言ってくれたら、僕らはそれを「良かったですね」って終えられるようにしていたいな、って。それはずっと僕らの中で持っていたんです。
お母さんたちの人生にとって少しでもプラスになるなら続けていきたいと思うけど、続けることが目的化されちゃうほうが、怖かったですね。
友廣さんが語る事業の「目的」については、書籍『OCICA—石巻牡鹿半島小さな漁村の物語』でも明確に語られていました。
この事業の本当の目的は、利益を最大化することではなく、お母さん方の笑顔を最大化させることなのだ。(本文より)
潔ささえも感じるこの事業目的は、すべての経営判断の軸であり続けました。
始めた当初は、東京でビジネスをやっているような方々が、売上を伸ばす方法とか多地域展開とか、良かれと思ってアドバイスしてくださったんです。ソーシャルインパクトという意味では規模を大きくした方がいい、というのが前提の社会なので、順調にいけばいくほど、そういうことをみんなに期待されて、一時期は僕らも混乱しました。
商品を軸にした事業なら、属人性をどんどん廃していって、人が入れ替わっても安定的に誰でもつくれる状態にするのが、一般的なビジネスとしては正しい方向で。でも僕らは、初めに「この人たちのために仕事をつくりたい」って思ったから、大変なこともあるかもしれないけど、属人性を残して、このメンバーでの個別解としての事業にしたかった。できるだけ一人ひとりの人が居る感じが残っていて、その伸びしろの部分で事業をつくっていきたいと思っていて。

輪切りにした鹿の角に糸鋸で細かな切れ目を入れていく作業は、相当の集中力を要します。得意・不得意はありながらも、自主練などを重ね、最終的には最高齢(80代)のお母さんもすべての工程を習得されたのだとか。 Photo : Lyie Nitta
それで、書籍をつくるときに「OCICAってなんだろうね」ってことを何回もメンバーで議論して、ブレイクスルーした瞬間があって。そこからは、ぶれないですよね。どんなことを言われても、「いや、目の前にいるこのお母さんたちの笑顔の最大化っていうのがこの事業のゴールだから」って。
お母さんたちがいっぱい稼ぎたいと思うなら売上を上げたいと思うけど、週2回作業して、月3〜5万円くらい稼いでるっていう状態が、当時はいい塩梅だったので、じゃあそこだよね、って。いつか「辞めたい」とか「卒業したい」って話が出てきたら、僕らがそこに合わせていくことができる状態でありたいね、って。
終えるタイミングまで、お母さんたちに合わせようという覚悟で向き合い続けることは、そう簡単なことではないでしょう。でも実際、牡蠣養殖が復活して多くのお母さんが卒業した2015年のはじめ頃に省エネモードにシフトしたのも、事業目的に即した経営判断の末のことでした。
11人中8人のお母さんが卒業して、でも廃業したり高齢で働けなくなった3人のお母さんたちは「なんとかして続けたい」って言ってくれて。お母さんたちにとっては、生きがいじゃないけど、やっぱり楽しいし、今まで出会えなかった人たちと出会える貴重な経験になっていると伝えてくれたんです。
じゃあどうしよう、って、運営体制を変えたんですよ。それまでは生産・出荷管理や品質管理は、「つむぎや」のスタッフが現地に常駐して担っていたんです。でも生産量が減るなかで、その人件費を賄えないと続けられないってなると、量を迫るようなことにもなりかねないし、本末転倒になってしまうんじゃないかって。
それで、「管理業務をやってもらえるなら続けられますよ」って話して、3ヶ月くらいかけて、売るところ以外はすべてお母さんたちに担ってもらう体制に移行しました。僕らはノルマを設定するようなことはせず、お母さんたちのペースでつくったものをいかにちゃんと売るか、という役割に徹して。お母さんたちがやりたいって言う限りは続けられる状態にしました。
ずっと続けられる体制ではありながらも、「人」を軸にする以上、終わりは「いつかやってくる」という気持ちでいたと友廣さんは語ります。そしてお母さんたちが主体的に「そのとき」を決めたのも非常に象徴的なできごとです。
僕に終えるって決断する権利はないな、って感じはずっとしていて。どこで明確に終えるかは僕が言わなきゃいけない立場なんだけど、でもなんか、OCICAって僕のプロジェクトって感じがまったくないんですよね。始めた当時のスタッフ、現場に入ってきてくれた仲間たち、デザイナー、販売してくださってきた方々、あと、お母さんたち。みんなでつくってきた感じがしているので。
全員とまではいかなかったんですけど、これまでのスタッフとお母さんたち、みんなで最後の確認を共有できたのは、本当に良かったです。
関わるメンバーの個別解としての事業を全うした先にたどり着いたのは、「終える」という全員の共通解。デザイナーさん、販売店さんなど、先んじて知らせた関係者のみなさんからのあたたかな言葉が寄せられる中、事業終了の準備を進め、ついに2019年5月22日、その経営判断をリリースしたのです。
「終え方」を意識して事業を進めるということ
続けられる。でも、いつでも終えられる。
そんな状態を保ち続け、納得感のある「終わり」を迎えたOCICA事業。これは復興プロジェクトという特殊な背景を持つビジネス特有のあり方であることは、確かです。でも考えてみると、事業目的に社会課題の解決を掲げるソーシャルデザイン領域においては、「課題が解決したら終える」というのは、自然な流れのようにも感じられます。
資金面や体制などが課題となり、続けられない状態になってやむを得ず終了という判断に至る事業が多い中で、友廣さんはどのようにチームや経営のあり方を整えていったのでしょうか。「終え方」のヒントを探りつつ、もう少し友廣さんと対話を続けてみたいと思います。
終えられる状態をキープするって、自分たちがどうやってでも生きていけるという自信がないとできない。だから、スタッフは意識していましたね。自立して生きている人に加わってもらおう、と。
僕らが「終わります」って言ったときに「明日からどうしたらいいんですか!?」ってなるメンバーだったら、終われないですよね。僕も過去に失敗したことがありますが、ほとんどの組織がそうやって変わっていくな、と思っていて。目的があって事業をつくっていく、っていう順序が変わっちゃう。それこそ労働者の権利もあるし、ミッションが「社会課題を解決する」ということから、いつのまにか「社員を養っていく」みたいなところに変わっていくんです。
僕らはみんな自立したメンバーだったから、お母さんたちの卒業もちゃんと受け入れられたし、みんなもゆるやかに、他の仕事に移行していくこともできた。今こうして話してて、その辺は大事だったな、と思いました。
「でもそれは、結果として、という話でもあって」。と、友廣さんは続けます。
OCICAを始めたときは、僕も物をつくって売った経験なんてなかったし、マネジメントみたいなのはできない前提で、みんなで持ちつ持たれつでやってきたというのが結果良かったのかな。
マネジメントの概念が無いほうが、結果的にみんな当事者的になって、成長するって言ったらおこがましいけど、伸びるじゃないですか、絶対。僕がリーダーで「育成」みたいな観点でやってると、僕のちっちゃい器の中でしか、その人たちのこと考えられなかったりする。だからいつも、極力マネジメントみたいなことをやらないでも回るような組織とかプロジェクトを考えているかもしれないですね。

Photo : Lyie Nitta
さらには、「余白」も友廣さんが関わるビジネスのキーワードのようです。
僕自身が“機能”として生きたくないと思っているので、人を機能に押し込めるのも、すごい嫌なんですよね。だから属人性を残しているんですけど、「じゃあ人が辞めたらどうするの?」って話もあると思うんです。でも、そのときはそのとき。
めっちゃ投資してギリギリでやってたら、たぶんそういうことが致命傷になると思うんですけど、それでも成り立つように、省エネというかベースを抑えて、余白を残して、上振れしても下振れしても受け止められるようにありたいと思っていますね。
全員が当事者意識を持つような組織、そして属人性から発生する「ぶれ」を受け止められる余白を残した投資と運営体制。「終わり」を見据えたビジネスのひとつのかたちが、見えてきました。
決してこれが正解とは思っていないんです。でも終えることの話はちょっと知っておくといいかな、って思います。終えた人の気持ちを知る機会ってあまりないですし、もしも法人を閉じるとしたら(※)それなりのお金もかかるし、ネガティブな理由で閉じる場合、大抵は誰かが粛々と敗戦処理をする、みたいになるんですよね。
特に地域で、自分のためじゃなく誰かのための事業をつくろうとする人にとっては、終え方を意識することは大事かもしれないですね。
(※OCICA事業は終えますが、OCICAを運営してきた一般社団法人「つむぎや」は継続するとのことです。)
次につなげるために「ちゃんと終えていく」
植物的な事業のあり方
属人性を残して、終わりを見据えて。友廣さんがつくるビジネスのかたちは、変わりゆくものに対して柔軟で、とてもしなやか。そのイメージは、ガツガツと経済的成長を目指す動物的なビジネスとは対象的で、控えめなのに芯の強さを持つ植物的なものに感じられました。そう伝えると、友廣さんはこんなことを語ってくださいました。
確かに、植物的ですね。僕は、事業って生き物みたいだな、と思っていて、勢いよく伸びる時期もあれば、成熟していく時期もあったり、それに対してガンガン肥料やって伸ばせばいいのか、って言えばそうじゃなかったりもするじゃないですか。
でもなんか、ひとつの種が実っていって、成熟期に入って、それなりに淡々と続いて、そろそろかな、って終わっていくっていうのは、ひとつの命の流れとしては、割と健やかな感じだったのかもしれないな、と思ったり。
森って、ひとつの命が終わっていくと、それがまた養分になって、芽吹いていくわけじゃないですか。老舗企業みたいに続いていくのがいいというのもわかるけど、1本の木が長く立つってことだけじゃなくて、巡っていくことの強さ、みたいなのもある。いっぱい芽吹いて、淘汰されて、淘汰されたものがまた次の木の養分になって大きくなっていくわけで、終わっていくのが悪いか、って言ったら僕は全然そんなこと思わなくて。
友廣さんの言葉を聞きながら、私は土壌がいっぱい養分を吸い込んで、次の芽生えを待っている森の中に佇んでいるような気分になりました。巡る命を感じられる、それはそれは、豊かな情景です。

Photo : Lyie Nitta
下手に延命治療みたいなのをして1本の木を100年残すよりも、タイミングが来たときに倒れて次の芽が芽吹いてきた方が、次につながっていくことになると思うから、ちゃんと終えていく。
人の人生で言うと、人生が続いていく限り、それがひとつの養分になって、また次により良いかたちで木が生えていくかもしれないし、自分の人生が終わってもまた次の人に引き継がれていくかもしれないし。かたちとして残し続けるということに執着しないでもいいんじゃないか、っていうのはすごく思っていましたね。
「長いほうがいい」とか「続けることが大事」とかっていう話が正しさとして語られていて、「終える」って言うと、失敗したんじゃないか、ってことになってしまいがちですよね。でも閉じないと次の扉って開かないから、もっと柔軟にやっていくのが当たり前になったほうがいいな、と思います。…いや、今話していて思ったな。再確認させていただきました。
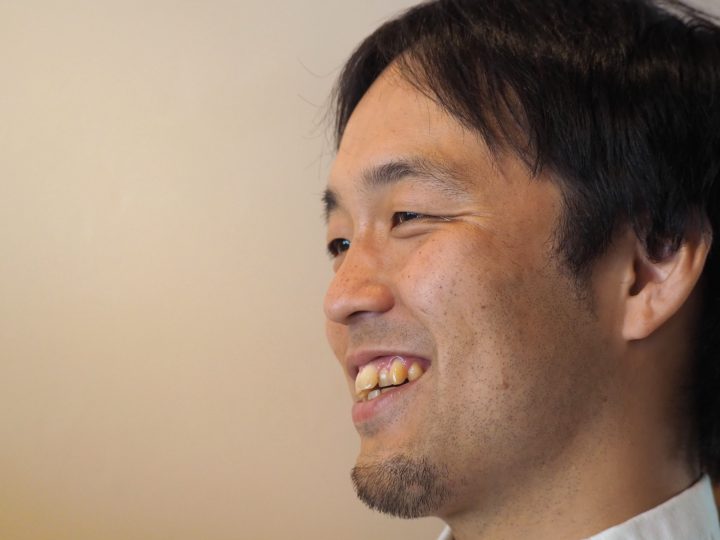
OCICAを終えても、友廣さんをはじめとする「つむぎや」のメンバーの人生も、お母さんたちの人生も、続いていきます。終えたことで蓄えた養分が、その後の人生で新たなかたちで芽吹くときは、きっとくるはず。「僕はOCICAさんに育ててもらいました」と振り返る友廣さんの晴れやかな表情を見て、私はそのことを確信しました。
以前、友人が「死に様は生き様」だと語っていました。そのときは、私にはその本当の意味は実感できませんでしたが、インタビューを終えた今、思うのは、ビジネスでも人生でも、終え方を見据えることは、ひょっとしたら、あり方そのものを見つめ直すことなのかもしれない、ということ。
「終える」ことを悲観視するのではなく、人生もビジネスも、「どう終えたいか」と考えると、見える景色が変わり、生き方もあり方も、変化していくのかもしれません。
あなたはどんな「終わり」を迎えたいですか?










