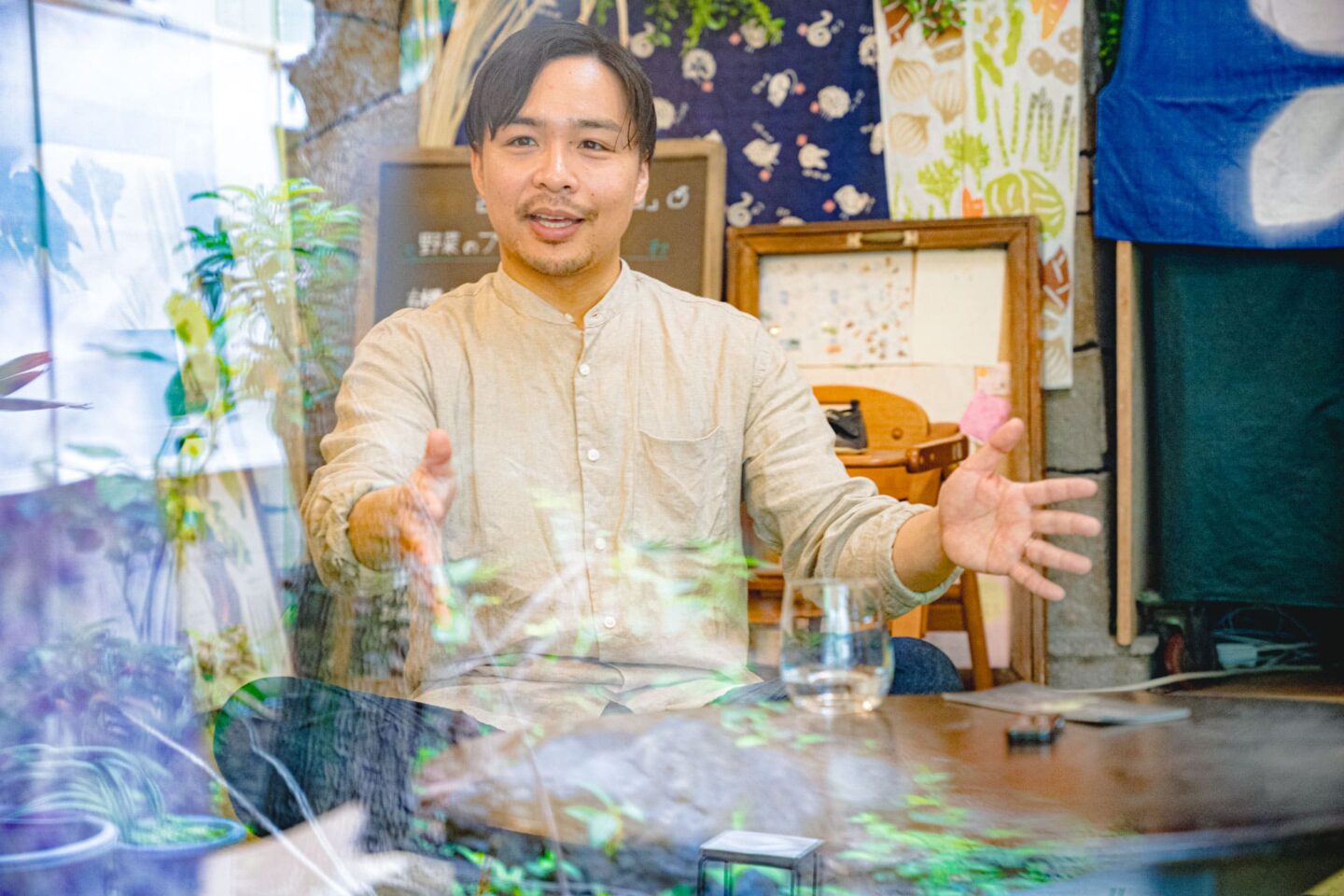「仕事」と聞いて、思い浮かべるものはなんですか?
日々の生活の大半を占めること。
生活のためにしなければならないこと。
就職活動中、働くことに不信感を抱き、キラキラとした様子で就職していく同級生たちをうらやましさと冷めた気持ちで見ていたとき。
あの頃の私には「仕事」はよくわからない、大きくて捉えきれないブラックボックスのようなものでした。
3年が経った今、「仕事」はいくつかの側面を見せ、それと同時に時間の過ごし方や自身のアイデンティティなど「自分」というものが浮き彫りになってきたように感じています。そして、その間に出会った人たちの「仕事への向き合い方」は、私に大きな影響を及ぼしています。
「仕事とは、自分を成長させてくれるもので、様々な景色を見せてくれる場所」
自分ごととして働いてきた人が口にしたその言葉は、私のからだに滞ることなく入り込み、すんなりと受け取ることができました。その人は、顔を合わせるたび熱く謙虚に語り、どうしてこんなにも精力的に活動を続けられるのだろうかと不思議に思う人なのです。
それが、「合同会社ひとつやねのした」の老沼裕也(おいぬま・ゆうや)さん。主に業界の課題解決のために農村・地域交流を目的とした企画事業や、企業・自治体の食農を軸としたプロジェクトへの参画、伴走支援を行っています。そして、足立区・東武スカイツリーライン五反野駅近くのご自宅を住み開きし、古民家「野菜日和」として、全国の農家の野菜販売をしながらコミュニティ運営を行っています。
「自分の心が動くことに仕事をあてはめているだけです。社会の考えるあたりまえを、自分にあてはめる必要はない」と語る老沼さん。
今回は、日本の農業を未来に紡ぐために農を軸に地域のつながりを大切にする老沼さんに、現在の活動に至るまでの経緯と自分軸で生きていくことの大切さについて伺いました。
埼玉県・川口市出身。高校卒業後、カナダの路上でホットドック販売をしたり、ロードバイクでカナダを5,000km横断。その後、オーストラリアにて農場で働きつつ、車で各地を周る。オーストラリアに滞在中23歳でパニック発作を起こし、日本に帰国。その後一年ほどの引きこもり期間を経て、社会復帰し、東京都足立区の市場の会社に就職。青果の責任者として5年ほど働いた後、九州から北海道まで農家を巡る旅を経て、現在の活動に至る。
コミュニティとしての青果販売・古民家「野菜日和」
野菜の販売や、農家と生活者が交流するイベントを行う古民家「野菜日和」(以下、「野菜日和」)は、2018年7月にオープン。老沼さんのご自宅の一部を店舗兼イベントスペースとして、ご夫婦で月に1度、野菜の販売を行っています。(2024年10月現在ご自宅での野菜販売は、第一子が生まれ育児専念中のためお休み中。12月15日に営業再開予定で、同日餅つき大会も開催されるそう。詳細は、古民家「野菜日和」のInstagramをご覧ください。)
「野菜日和は、僕の気持ちを具現化した場所なんです」と、老沼さん。
当初から、農産物の魅力や農家の思いを伝えるためには、単に青果を販売するのではなく、コミュニティとしてお客さんとの関係性を育む必要があると感じていたのだとか。
5年が経ち、現在はたくさんの人で賑わい、600点ほどの野菜は毎回完売してしまうほどですが、はじめた当初は雨で客足が遠のくことで、売れ残りが出たり、仕入れ量が少ないがゆえに輸送費が高くついたりと、課題もあったといいます。
「野菜日和」をはじめたときは、30歳。「野菜日和」を含め、独立して事業を始めた際は、大変なことがいくつも重なったのだとか。
そんな時期を乗り越え、「野菜日和」の野菜販売回数は、2023年12月には102回目を迎えました。活動を始めてからの一年間は特につらかったと振り返る老沼さんですが、それでも続けてきたのはなぜでしょうか。
本当に食や農に思い入れがなかったら、ここまで続いていないかもしれませんね。やっていることはすごく小さいし、周りからのやっかみもありました。それでもやり続けなければいけないと思ったのは、自分が本当に貢献したい人たちと、農産物の世界があったから。だから「心の種蒔き」を続けてこられました。

「野菜日和」開催100回記念のマルシェの後の食農会の様子。農家さん、「野菜日和」を始めたときから「野菜日和」に通う、家族ぐるみの付き合いのご家族、足立区の自然食品店「はる菜」さん、そして老沼さんのお宅の大家さんを交えたトークイベントも(撮影:小野 悠介)
そして、「野菜日和」では、農家と生活者の関係性を構築するために、畑での交流やCSA(※1)、勉強会、食事会などを開催しています。
※1 “Community Supported Agriculture”の略称。日本では、「地域支援型農業」と呼ばれている。消費者が生産者に代金を前払いし、天候不順などによる不作のリスクを生産者だけが負担するのではなく、コミュニティの中で農業従事者を支える仕組み。(「CSA(地域支援型農業)とは・意味」より)

地域の方が刈った竹を使い、子どもたちとつくるところから開催した、新潟県十日町の流しへぎそばの様子。他にも醬油絞り体験会や、年末には毎年餅つき大会を行い、多くの地域の方が参加している(撮影:小野 悠介)
また、自宅を「住み開き」する「野菜日和」のほかにも、足立区浴場組合(主催)と全国7地域が連携した「香り湯プロジェクト」の企画・運営では、規格外および、余剰農産物の利活用という側面だけでなく、都市と農村の交流をより活発にしながら、各地域の農産物や、銭湯文化の魅力を発信しています。

全国で生産される農産物の約2~3割は、規格外農産物と言われているそう。足立区内の銭湯では、さまざまな地域と連携して「香り湯プロジェクト」を行っている。徳島県神山町の「すだち湯」のほか、大分県臼杵市の「かぼす湯」、山口県萩市の「みかん湯」、長野県山ノ内町・秋田県鹿角市の「りんご湯」、熊本県八代市の「いぐさ湯」、愛媛県の「いよかん湯」を実施
そのほか、主として、「国消国産・持続可能な農業のあり方」をテーマに、「有機農業」「地域コミュニティ」「規格外農産物の利活用」「都市農村交流」「遊休地活用」など、生産拡大に向けた流通課題の解決や販路拡大の支援、プロモーション企画など、業界の課題解決のため、全国各地を飛び回りながら、自治体や企業の食農プロジェクトに参画し、幅広く精力的に活動しています。
23歳でひきこもりに。農産物の世界に助けられた
それにもかかわらず、「相当遠回りをしてきた」と老沼さんは話します。
老沼さんは、高校卒業後、自分のやりたいと思うことをやり続け、20歳でカナダに渡航。路上でホットドックを販売したり、危険地域だと言われるエリアに暮らすホームレスの人たちとの交流を楽しんだというエピソードも。そして、自転車でカナダ5,000kmを横断。その後、オーストラリアでは季節労働をしながら車で旅をしていました。その途中、23歳で突然パニック発作を起こし、緊急帰国。日本の心療内科でパニック障害と診断され、一年ほど引きこもり生活を余儀なくされます。
玄関のドアノブにも手をかけられないほどのパニック発作が起こり、家に引きこもる日々が続きました。
若い時って何もないけど、希望が溢れている時期ってあるじゃないですか。でも、そこから一気に何もできなくなった自分がいて、もう本当に「無」に近い状態だったんですね。希望も夢もなくて、見えないトンネルをずっとさまよっているようでした。未来のことややりたいことを考える余裕すらもなかったです。
そんな中、地元の親友が外に連れ出す機会をつくってくれ、外に出て、人と話し、少しずつ社会との接点を取り戻していきました。そして、昼間の仕事をしようと通勤ラッシュに重ならず早朝から勤務でき、人との関わりがそれほど多くないという理由から、青果市場の流通会社に就職します。
働きはじめたら、またまともな生活に戻れるという願いを抱き、どんな仕事でも、自分を拾ってくれた会社やその業界のなかでとことん頑張ってみようと入社。初出勤の夜明け前、上司に連れられ、はじめて市場に足を踏み入れたとき、農産物に関わる仕事を一生続けていこうと、おのずと決心できたと言います。
普通だったら「あ、市場ってすごいっすね」ぐらいで終わると思うんですが、それまでずっと家に引きこもっていたから、市場の騒がしさの中で色鮮やかな農産物がやり取りされる、そうした世界に本当に魅了されたというか。今でも思い出すんですが、いろいろな青果の色鮮やかな世界や香りに五感がぱっと生き返った感じがしましたね。自分の心に明るい火が灯った瞬間でした。この感覚がなかったら、たぶん今の自分には行き着いていなかったかもしれません。
そんな初出勤日を経て、老沼さんは、介護施設や病院などへの農産物の配達と営業を担当。人と接することに対してのハードルは当時まだ高く、しどろもどろになりながら野菜の説明などを懸命にしていました。
そして、仕事終わりにスーパーや八百屋を巡り、野菜や果物の食べ比べをして特徴や扱い方を学び、取引先や社内メンバーからも農産物について聞かれることが徐々に増え、60年続く企業において史上最年少で青果仕入れ責任者に。青果に関することをすべて管理できるようになった老沼さんは、青果仕入全般はもちろんのこと、社内教育や業務改善、青果広報、休開市日(※2)に捉われない会社の休業日の改革など、多岐に渡る業務を行うようになりました。
※2 市場の独自に定められた休業日のこと
今でも、農産物の世界に助けられたと感じているんです。自分の中で誰にも必要とされていなかった時期があったけど、働きはじめていろいろな人に頼られ、学んで成長を感じられて、自分の居場所はここなんだ、とすごく安心感を感じましたね。
引きこもっていた時間を取り戻したいという気持ちで、がむしゃらに働き、野菜が好きすぎて、勤務時間外でも常に野菜のことばかり考えていたという老沼さん。はじめてできた後輩に、冗談交じりに「野菜愛が気持ち悪い…(笑)」と言われたこともあったほどでした。
29歳で仕事を辞め、農家を巡る学びの旅へ
それほどのめり込んで仕事をしていく中で、農産物を扱う業界の課題がいくつか見えてきました。その中で、台風や洪水といった自然災害で、産地が被害を受けた際の責任者としての取引先への説明は、二次情報から拾っていましたが、一次産業の現場を見たことのない自分自身が口にする言葉に徐々に違和感が募っていきました。
「一次産業のことを、もっと知らなければいけない」という問題意識を持ちながらも、日々の忙しない業務に追われるなか、2016年の台風被害が起こりました。九州から北海道を横断するかたちで4つの台風が日本列島に上陸。北海道は全国の農産物の生産量の約17%を占め、夏から秋にかけて出荷のピークを迎えます。台風の被害は、秋の収穫前の重要な時期と重なり、人参や玉ねぎ、じゃがいもなど定番の野菜は市場から姿を消しました。(※3)
※3 2016年8月に、台風第7、9、10、11号が北海道、東北、関東地方に相次いで上陸。道内の農業被害金額は計543億円に達した(「2016年の北海道における台風による農業災害」より)
それでも当時の老沼さんの仕事は、病院や介護施設などに食材を届けること。代替品として一時的に海外の農産物を仕入れる判断を余儀なくされます。
そんな台風被害から数ヶ月が経ち、人参や玉ねぎなどの産地は九州へと切り替わり、野菜の相場も戻りつつありました。それでも、国産より数十円安い海外産の食材を引き続き仕入れたいという取引先も。そんな現状に、老沼さんは強い危機感を覚えます。
今までいろいろな自然災害や天候不順で農産地に被害が出て、その度に野菜の相場が乱高下してきました。買い手は、少しでも安い海外の野菜を買う。このままで日本の農業は大丈夫なのかと漠然とした思いがあって。今は、安い海外の農産物も、将来的にはどうなるかわかりません。もし日本国内で農産物を生産できなくなったら、僕らの食の未来ってどうなるんだろうってすごく思ったんです。2016年の台風をきっかけに、自分が助けられた、自分の好きな業界をより真剣に考えなくてはいけないと思いました。
食の未来や日本国内の農業を頭で考えているだけでは、答えは導き出せない。一次産業の現場に足を運び、とにかく農家の声を直接聞かなければいけない。当時29歳で、農家を巡るために、5年ほど勤めた会社を辞める決断をした老沼さん。仕事を辞めることへの不安はなかったのでしょうか。
パニック障害が完治しない中でも、僕を支えてくれていた社長には感謝の気持ちが、今でも心にあります。ただ、今後も農産物に携わる仕事をする上で、各地の生産現場を見て、農家さんのリアルな声を聞いてまわることは自分にとってはプラスになると思っていました。そのタイミングが20代の今しかないと。この旅は、よく言われる独立するための旅ではなく、学びの旅だったので、旅が終わったら農産物を扱う会社に戻ろうと思っていました。
そうは言うものの、旅をする前、現在の「野菜日和」のようなイメージは少なからずあったのかとお聞きすると、老沼さんの仕事の捉え方がハッキリと滲み出る答えが返ってきました。
あるか、ないかというよりは、別に考える必要もなかったかなと。何をするかという問いは、たぶん職業にとらわれすぎている。その業界の知識や経験が増えていけば自ずと一つの仕事だけじゃなくて、いろいろな仕事のあり方で貢献できると思っていました。
現在、環境保全型農業や有機栽培の農産物を推進する姿勢を持ちつつも、農薬や化学肥料を使用する慣行栽培の必要性も同時に説いている老沼さん。その考えに至った背景には、農家を巡る旅がありました。
車に布団と長靴、作業着を積み込んで、東京から九州まで車を走らせ、農家の手伝いをしながら、北海道までおよそ一年かけて日本列島を横断。
日本の農業の課題を自分の目で確かめ、農業全体を俯瞰することが目的だったため、慣行栽培、有機、自然栽培など栽培方法や、F1種や在来種など扱う種の種類、大規模、小規模農家など、あえてさまざまな農家を巡りました。中には、有機農家が慣行農家を紹介してくれる場合もあったそう。
旅の初日、九州のとある出荷グループの部会長に話を聞き、3日間お世話になりました。化学肥料や農薬が多く使われていることで、産地が疲弊して、病気も出て、大変だと。その後、多くの農家を巡る中で、農業の持続可能なあり方を、環境視点で考えると農薬や化学肥料はできるだけ少ないほうがいいのだと感じ、九州にいるあいだに考えがかなり有機に偏っていきました。
そんな中、ある地域で有機寄りの考えを持つ農家や若者たちが集まり、近所の慣行栽培の農家からもらった野菜を「あんな農薬がかかったものは食えない」と笑いあって話す場に居合わせた老沼さん。
その時に僕、ものすごい違和感を覚えたんです。確かに有機野菜は農薬がかかっていないものが多いけれど、農薬を使っている農家さんの野菜をさげすむ行為が正しいとは思えなくて。苦労して野菜を育てている人の努力を踏みにじるような考えを持っちゃいけないなと思ったんですよ。
農薬や化学肥料を減らしていく考えはすごく大切かもしれないけど、農薬や化学肥料を使っている人たちを否定してしまったら、日本の農業はいい方向に変わらないんじゃないか。それ以降、分断ではなく共存・共生する形をとりながら、持続可能な農業の可能性を考えるようになりました。
すでに自分にあるものを、少しずつ積み重ねていく
そして、農家を巡る旅の後半、山形県真室川町で代々続く農家、髙橋伸一さんとの出会いによって、自分だからこそ担える役割に気づきます。
伸一さんは「ないものねだりからあるもの探しへ」の考えでした。地域の伝統工芸の藁細工や伝承野菜を紡ぎ、脈々と受け継がれている暮らし方をあたりまえのようにして、農法や種に対して白黒ではなく、強い主張をせず淡々と自分たちにとって大切なものを見極めていく。何者かになろうとするのではなく、自分にあるものを少しずつ積み重ねていくことが大切なんだと思ったんです。
多くの農家との交流を経て、旅の後半に「自分でも農業をやってみたい」と思いはじめていた老沼さん。ところが、伸一さんに「僕は土の人だけど、君は風の人だよね」と言われたのだとか。
「土の人」と「風の人」が合わさって「風土」がつくりあげられるという話を聞いたときに、自分の役割として土の人である農家をサポートする、農家の手が回らないことをやるのが自分の使命だと感じました。東京にいるからこそできる役割を探していこうと。
足立区という場にしっかりと根を張りながらも、「風の人」として地域内外の人とさまざまな活動を共に行う。その様子は、日々のSNSでの発信などからもわかります。

東武スカイツリーライン西新井駅・梅島駅・五反野駅の界隈に点在する店舗の店主たちが結成した架空の商店街「ナナシノ商店街」では、ぬいぐるみカフェやガーデニングスタジオなど個性豊かなお店がつながり、不定期でイベント開催やマルシェの出店などを行っている(写真提供:足立区)
他人の生き方に惑わされすぎないで
こんなふうに精力的に活動されている老沼さんですが、お会いして話すたびに、どこか弱さを受け入れるような優しい姿勢を感じられるのです。今回のインタビューで、老沼さんがこれまで経験してきたつらい時期が背景にあったのだと思いました。
職業や生き方で目立つ人とか、かっこいい生き方をしている人もたくさんいると思うのですが、あまり惑わされないほうがいいかなと。他人軸じゃなくて、もっと自分の心の声を聞いてほしいなと思います。人の話は聞きたがっても、自分の声を聞かないことが多いなって。僕は引きこもりの時、それをすごく感じたんですよ。
この言葉を聞いて、何者かになろうとしたり他人と比べて焦るのではなく、自分の人生として何ができるか、自身の声を聞きながら生きていくことで、自分が進んでいきたい道がおぼろげにでも見えてくるのではないかと思えました。
20、30代なんて人生のピークではないと思っています。日本の多様な食や農、地域を自分ごとに考える人を増やす、という僕の行動理念の一つである「心の種蒔き」の芽が出てくる、人生後半の伏線回収が僕の楽しみです。
僕は、食や農に関することが好きで仕事をしていますが、それは楽しいことばかりではありません。つらいことや悔しいこともたくさんある。それが社会に合わせて生きていくということです。だからこそ、学ぶことや挑戦することを続けているんです。
私は20代が人生の盛りのような、若さがもてはやされるような風潮を日常の中で感じることがあります。そういった雰囲気に少し違和感があり、人生のピークがそこならば、その先も続いていく時間をどんなふうに捉え、生きていけばいいのだろうかと頭をもたげるような感覚になることがありました。
けれども私は老沼さんの言葉を聞いて、これからも続いていく人生を長い目で見て、目の前のことに集中してがんばったり、楽しんだりしていきたいと思いました。自分自身に信頼を置いて、これからも続いていく人生を生きたい。
人が熱い想いを抱いて動いているのを見ていると、そのエネルギーをもらって、私もやってみよう!という気持ちになるのです。
みなさんもぜひ、行き詰まるようなことがあったら、身近で熱い想いを抱いて動いている人を探してみてください。そして、その人と話して、その想いを感じてみてください。きっと、自分の中にもある大切なものが見えてくるはずです。
(撮影:イワイコオイチ)
(編集:増村江利子)