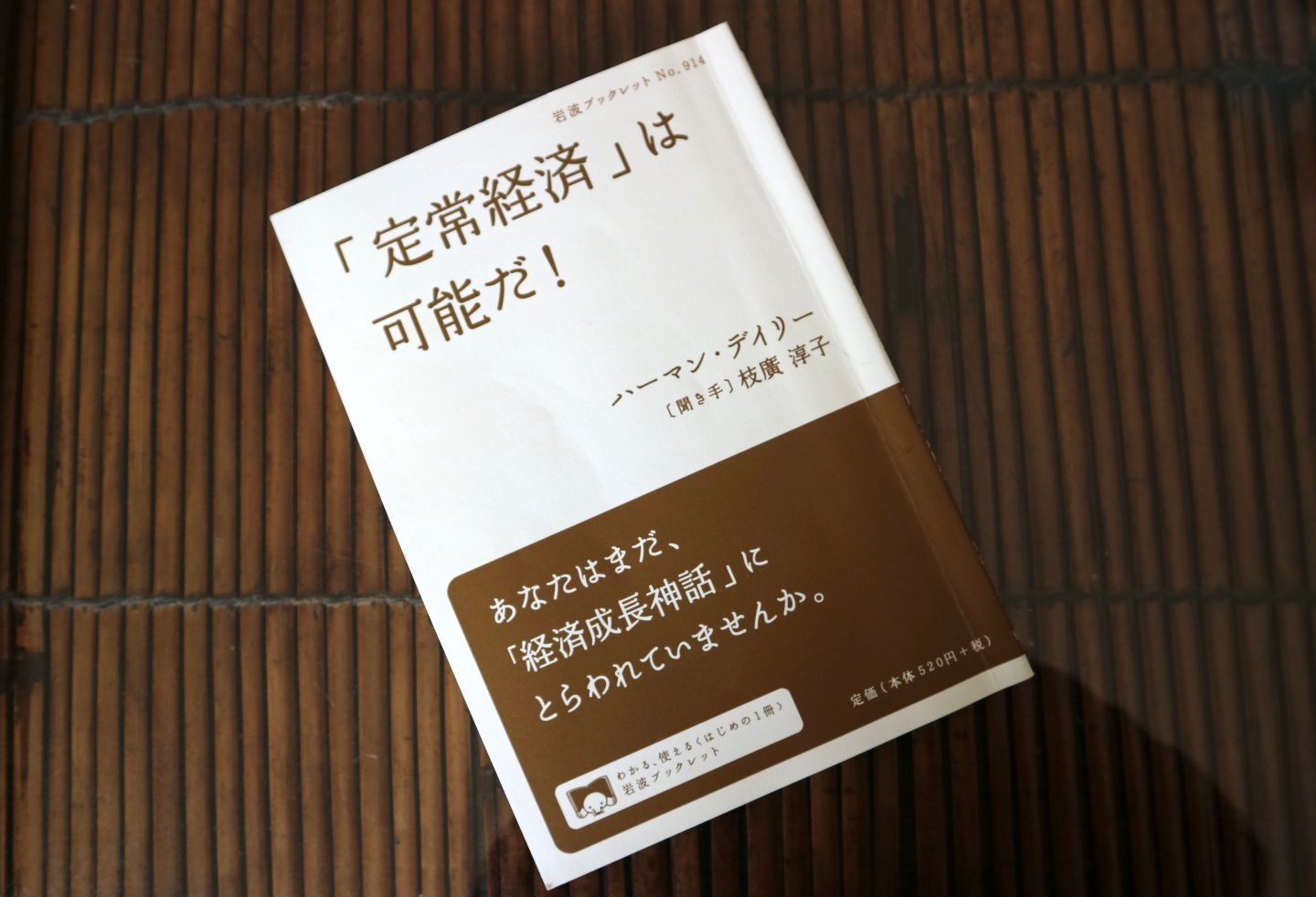ここに、とあるアンケートがあります。質問項目はふたつ。
「日本にとってGDPが成長しつづけることは“必要”だと思いますか?」
それでは
「あなたはGDPが成長しつづけることは“可能”だと思いますか?」
「幸せ経済社会研究所」が2017年に行った「経済に関するアンケート」のリサーチで、その結果は、GDPの成長が「必要」「どちらかと言えばそう思う」人は合わせて66パーセント。一方で、成長し続けることが「可能」「どちらかと言えばそう思う」と答えた人は35パーセントにとどまりました(*1)。つまり、経済成長は必要でも、無理だと思っている人が多いという矛盾した結果です。
これは現代の私たちの心情をとてもよく表しているように思えます。経済成長しなければ景気が悪化し、給料もあがらずほしいものが買えない。貧困や福祉、社会保障にもお金がまわらなくなる。でも果たして成長し続けられるか? と問われると、人口も減るし現実的ではなさそうな……といったところでしょうか。
これまでとは違う経済のアプローチやシステム、指標を求めて、実践や検討を始めている人たちに話を聞きにいく連載「ローカルから始める、新しい経済の話」。
今回は、環境ジャーナリストで、新しい経済や社会のあり方を研究されている枝廣淳子さんにお話を伺いました。枝廣さんは「定常経済」を提唱する米国の経済学者ハーマン・デイリー氏にインタビューした本を出版し、その考え方をセミナーなどを通じて紹介しています。

日本の環境ジャーナリスト、翻訳家。大学院大学至善館教授、幸せ経済社会研究所所長。東京大学大学院教育心理学専攻修士課程修了。有限会社イーズ代表取締役。映画『不都合な真実』『不都合な真実2』(アル・ゴア氏著)の著書翻訳をはじめ、環境・エネルギー問題に関する講演、執筆、CSRコンサルティングや異業種勉強会等で活動。
私たち人間は地球という閉鎖されたシステムに暮らしている
「経済成長は必要か、否か?」への答えの前に、枝廣さんは、まず大前提となる考え方から話してくれました。
枝廣さん 大事なポイントは、私たちは地球という閉鎖されたシステム上に暮らしているということです。
外から入ってくるのは太陽の光エネルギーのみで、出ていくのは宇宙への熱放射のみ。雨が降るのも、どこかから新しい水がくるわけではなくて、地球上の物質が形を変えて循環しているにすぎないわけです。
人はあらゆる資源を地球から取り出し、加工したり消費して、また別の形にして地球に戻している。それが経済活動です。石油を取り出して、燃やして二酸化炭素を戻すのもその一つ。この出し入れをスループットと呼び、スループットには、地球1個分が処理できる量という限界があるのです。
地球が生み出せる資本(森林、淡水、水産物など)も、人が出すCO2や廃棄物を地球が吸収できる力も、上限が決まっているということ。
枝廣さん ところが今は地球が生産できる資源より、人が使う資源の方が上回っています。地球1個分の扶養力を1とすると、現在はそれをはるかに越える1.7を使っている。地球が1.7個なければ足りない。足りないぶんは、未来の前借りをしているということです。
地球に過剰な負担をかけながら経済成長を求める社会に疑問を抱くなかで枝廣さんが出会ったのが、アメリカの経済博士、ハーマン・デイリー(1938-)(*2)の提唱する「定常経済」でした。定常経済とは、地球が処理できるレベルに生産量を落とした上で、スループットを一定に持続していこうとする経済のあり方。
枝廣さん でもとてもややこしいことに、“定常経済=GDPが一定”ということではありません。
スループットを低く抑えて保つ定常経済のなかでも、一つの資源から2倍のものをつくるなど、経済活動を活性化することは可能です。
つまり、枝廣さんの意見をまとめるなら、「地球の処理量を超えての経済成長には反対だけれど、その範囲内でGDPが増えるのは悪いことではない」といったところでしょうか。
「定常経済」とは何か?
定常経済を提唱したハーマン氏はアメリカの経済学者です。1988〜1994年の6年間、世界銀行で「持続可能な開発の政策づくり」に携わった人物でもあります。
枝廣さんがハーマン氏に丁寧に質問を重ねているインタビュー本『「定常経済」は可能だ!』(岩波ブックレットNo.914)を参考にすると、定常経済とは以下のようなことです。
ハーマン氏「経済は、地球の範囲内で営むしかありませんから、地球のサブシステムなのです。経済がどんどん成長して、地球全体を覆うほどになったとしたら、それ以上は成長できません」(P11)
地球の大きさに比べて人の数も人工物も小さかった時代には成長の余地があったものの、世界人口の増えた現代、私たちは自然資源を使いすぎている。発展途上国など貧困に苦しむ国々ではまだ経済成長が必要かもしれないが、世界全体でみれば成長を抑えて、地球から出し入れする資源を低く保つことが必要でしょう、と。
ただ、経済成長なしに「貧困や失業、社会保障の問題などをどう解決するのだ」という反対意見もあります。これに対してハーマン氏は、一見成長しているように見える経済も、環境的・社会的コストを計算に入れれば、じつはすでに「不経済成長」(つまり成長していない)に入っていると説明します。
ハーマン氏「生産の便益を測っているだけで、それに対して払っている「環境的・社会的コスト(犠牲や代償、費用など)を測っていないからです。経済成長が生み出す“富の副産物”の問題に、知らん顔をしているのです」(P14)
ここで言う「環境的・社会的コスト」とは、温暖化、核廃棄物、原子力発電のリスク、油田の枯渇、森林消失、表土の浸食、生物多様性の危機……などを指し、他にもいくらでも挙げることができます。
ハーマン氏はこの「環境汚染の経済的な損失」を考慮に入れて計算した持続可能経済福祉指標(ISEW)と、「人の幸福に影響を与える項目」を加えた真の進歩指標(GPI)を開発し、GDPとの相関関係を調べました。するとある時点から、GDPが増えてもISEWやGPIは増えなくなるという結果に。
ハーマン氏「1980年ぐらいまではGDPとGPIが正の相関を持っていたのですが、そのあとは、GDPは上昇を続けているのにGPIは横ばいです。環境破壊などの費用が増しても、福利や幸福といった便益は増していない。
もうひとつの証拠は、自己評価による幸福度の測定です。様々な幸福度の研究によると、幸福度の自己評価は、一人あたりのGDPが年2万ドルくらいになるまでは、一人あたりのGDPとともに上昇します。そして、そこで上昇が止まるのです」(P15)
所得は充足ラインまでは重要でも、それを超えると、幸福の決定的要因となるのは、友人関係、結婚、家族、社会的な安定性、信頼、公正さなどになってくると言います。そこにGDPは関係ないのです。
では、どうすればよいのでしょう?
ハーマン氏の提案は、まずは地球資源の範囲内に経済活動を抑えること。たとえばCO2の排出量を世界で割り振り、足りない分は余っている人からお金で買うようなしくみにすればよいという方法です。しかし、世界中で足並みを揃えるのはとてもハードルが高そう。現にいまそれができているわけではありません。
「地球に暮らしている限り、定常経済の考え方は原理原則だと思います。でもそれを今の状態からどう実現するか?がもっとも大事で、難しいところなんです」と枝廣さん。
そこで「ローカル経済」が登場します。

静岡県駿河湾のサクラエビ漁で実現できた「定常経済」の事例
地球規模の話はなかなか身近に感じることができなくても、特定の地域に範囲を絞ると「定常経済」が見えやすいのです。
教えていただいたのは、静岡県駿河湾のサクラエビ漁の事例。
サクラエビは日本では駿河湾でしか捕れません。ここがポイントです。1年間の売上は湾界隈の3つの漁協合わせて40億円を超えます。
かつては1年中漁を行っていましたが、漁獲競争による捕り過ぎが原因で、1964〜1965年頃に漁獲量が急激に減りました。このままでは、いずれサクラエビ漁はできなくなってしまうと危惧した漁師たちは話し合い、漁をする時期を3〜6月上旬の春漁と、10〜12月下旬の秋漁の2回に制限。さらに、「プール制」と呼ばれる制度へ移行することにしました。
プール制とは、全体で捕る量を制限し、捕れた船もそうでない船も、売上金を平等に配分する方法。1966年、まず由比漁協が試験的にこの方法を導入します。1968年に魚の捕れすぎで価格が暴落し、50トンのサクラエビが海に投棄されるという事態が起こった時には、プール制が価格の安定化にもつながることが証明され、1977年に残り2つの漁協も合わせて総プール制が始まりました。
枝廣さん 実際にどうしたかというと、夏に漁師さんたちが試験管で産卵調査を行うんですね。
水をすくって卵の数を数えると、その年に生まれるエビの数が推測できる。一年で増える分量だけを捕る、でも元本には手をつけないで、翌年へ持続させるのです。毎回、多くの船が一斉に漁に出ますが、それぞれの網でどれくらい捕れたかをその場で申告して、本部が足し上げていき、一日分の上限に達したら今日はもうおしまい、というわけです。
この制度に切り替わっていなかったら、もう今頃は漁ができていなかっただろうと地元の漁師は話しました。
競争の激化は、必要以上に捕ろうという気持を煽り、資源の枯渇を加速させます。いま地球規模で起こっているのも、これと同じ、人より少しでも多く稼ごうとする競争による加速です。
「定常経済=GDPが一定」ではない
このサクラエビ漁では、定常経済が実現されましたが、先述したように、「定常経済=GDPが一定」とは限りません。漁獲量は一定に抑えつつも、さまざまな工夫で売上をあげる実践が行われてきました。
1999年には漁協直営の直売所、2006年には食堂「浜のかきあげや」がオープン。直売所では釜揚げされた新鮮なサクラエビやもう一つの特産品シラスが販売され、食堂ではおいしいかきあげや丼を食べられます。
2016年の年間売上は合わせて3億円。漁協では「沖漬け」「漁師魂」などの加工品も開発し、漁期以外にも収入が確保でき、以前よりも収入が安定したのだそう。さらには、水揚げしてすぐに死んでしまう性質のサクラエビを生きたまま都会に届ける技術を開発し、「活きサクラエビ」として高値で販売できるようになったことで、域内GDPは結果的に上がっています。
枝廣さん もともと経済がローカルの中だけでまわっていた時代には、ある意味、定常状態に近かったんですよね。たとえば江戸時代の平均GDPの成長率はわずか0.4パーセントと言われています。それが、効率・分業の考え方が浸透して、移動手段が発達して、グローバルに交易が行われるようになりました。
けっしてグローバル経済を否定するわけではないし、一地域内ですべて閉じた方がいいという話ではないんです。ただ、今あまりにも過度な生産と消費で、すでに地球の許容量を超えてしまっている。そして各地域に目を向けると、自分たちの食べものやエネルギーなど外部に依存する度合いが高すぎて、リスキーな状態にある。
まずは各地域が自分たちの自然資源を持続できる形で循環利用して、自分の足で立てる、経済の自立の割合を増やし、バランスを取った上で、他の地域と相互依存するのがあるべき経済の姿ではないかと思うんです。
地球の資源が限られていることには、多くの人が気付いています。それでも経済成長することを前提につくられた社会に生きていて、ペースを緩めることができずにいる。
駿河湾の事例は、現状を定常経済に近づけるために、ローカルからのアプローチが有効であることを示しています。
さらにこれは、地域社会の持続を考える上でも重要なこと。引き続き、新しい経済のあり方を探りに、取材を試みたいと思います。
(*1)「経済に関するアンケート」マクロミル インターネットリサーチ、2017年3月16日〜18日実施、20〜70歳の1248人を対象にした調査。
(*2) Herman Daily(ハーマン・デイリー)1938年生まれ。バンダービルト大学経済学博士、ルイジアナ州立大学教授、世界銀行上級エコノミストなどを歴任。現・メリーランド大学公共政策学部名誉教授。経済学に環境、地域社会、生活の質、倫理性といった要素を組み込んで“定常状態の経済学”を再定義し、環境経済学の礎を築いた。
※この記事は2017年12月に東京で行われた枝廣さんの第73回読書会での講義と、後日個別に行ったインタビューをもとに構成しています。
(Top Photo: photoAC)