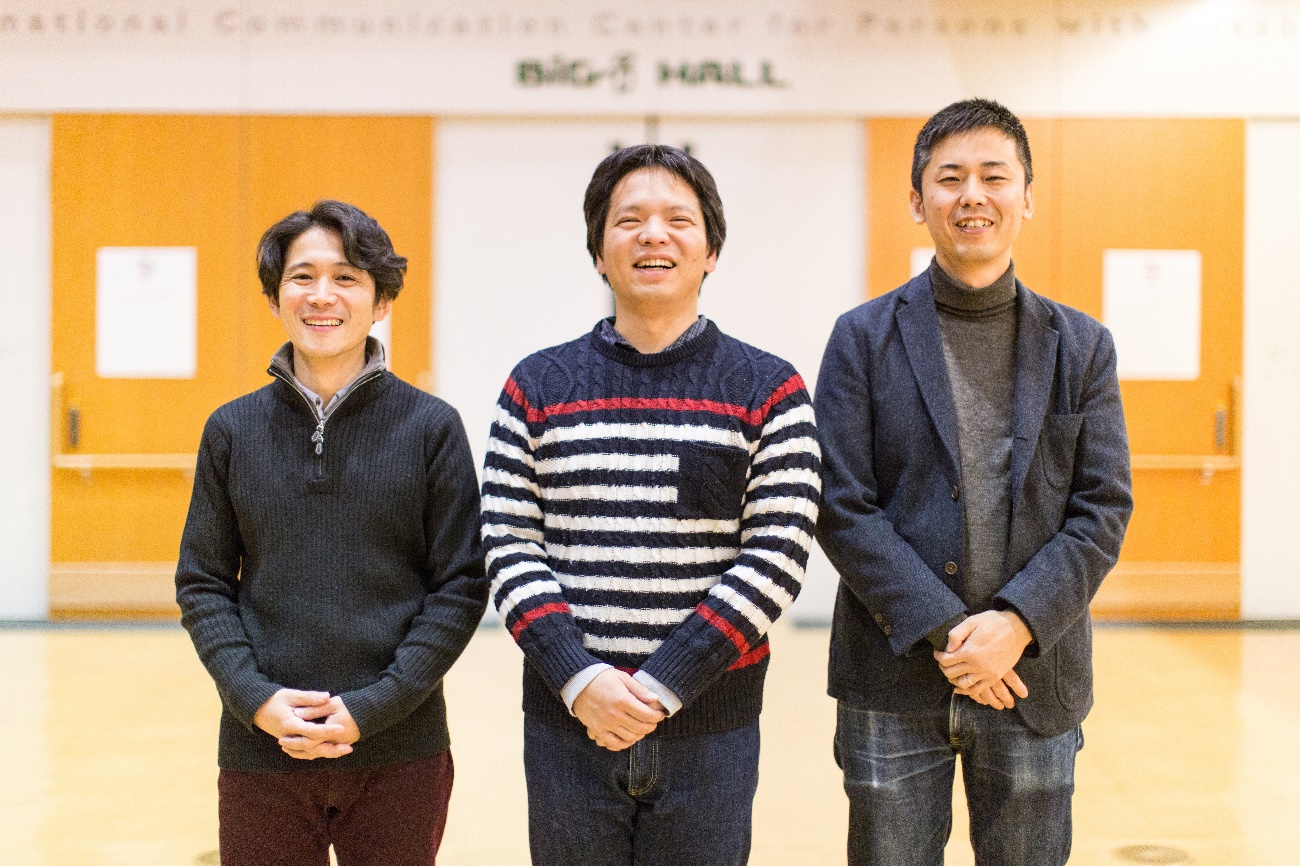子どものころ、夢や憧れへのきっかけを与えてくれたのはどんな人でしたか? テレビや新聞で目にした遠くの“ヒーロー”の背中を追いかけたという人もいれば、両親や地域に暮らす年長者など近しい大人の姿に影響を受けた人もいるでしょう。
「じゃあ自分は、次の世代を担う子どもたちのために何ができるだろう…。」
もしあなたがそんな迷いを抱えているのなら、さまざまな人が暮らすニュータウンで行われている取り組みからヒントがもらえるかもしれません。
ニュータウンとは、1960年代から都市の郊外に開発された市街地のこと。泉北ニュータウンは2017年に、まちびらき50周年を迎え、住民・企業・行政が連携して「泉北ニュータウンまちびらき50周年事業実行委員会」を結成。新しい市民主体の取り組み「SENBOKU TRIAL」が行われています。
今回登場していただくのは、「子どもプログラミング サポーター100人プロジェクト」の田重田勝一郎さんと、「みんなが主役!泉北吉本新喜劇プロジェクト」の野口正文さん、そして公の立場からお二人の活動を見守ってこられた堺市役所市長公室ニュータウン地域再生室の中川健太さんです。
写真左。特定非営利活動法人 志塾フリースクールラシーナ 理事長。ITエンジニア。プログラミングに興味がある子どもに学べる場を提供したいという思いから、2016年2月に「CoderDojo(コーダードウジョウ)堺」を立ち上げ、無料のプログラミング道場を毎月運営している。泉北ニュータウンまちびらき50周年事業では、南海電気鉄道株式会社の支援を受けて「子どもプログラミング サポーター100人プロジェクト」を展開。
写真中央。泉北高速鉄道・車掌。泉北ニュータウンまちびらき50周年事業では、堺市南区役所の支援を受けて「みんなが主役!泉北吉本新喜劇プロジェクト」を展開。2017年11月23日に堺市立栂文化会館で「泉北吉本新喜劇」の公演を開催した。
写真右。堺市役所市長公室ニュータウン地域再生室主査。泉北ニュータウンまちびらき50周年事業実行委員会の事務局として、「SENBOKU TRIAL」の活動を支援した。
はじまりは、小さな後悔と素朴なモチベーション
まずお話を伺ったのは、「子どもプログラミング サポーター100人プロジェクト」の田重田さん。もともと、企業でシステムエンジニアとして働いていました。
田重田さん 自分がプログラミングを学んでいたころ、まわりに教えてくれる人がいなかったことを、ずっと悔やんでいました。もしそばに誰かいたら、もっといろいろな力を身につけていただろうな、と。そうするうちに、「子どもがプログラミングを学べる場をつくりたい」という思いを抱くようになったんです。
ほかにもかねてから自分の時間を使って取り組みたい事業があったため、田重田さんは一念発起して会社を辞めて独立。そうしてフリーのエンジニアとして仕事をしながら思いを実現するための情報を集める中で、ある時大きなきっかけが訪れます。
田重田さん とある本を読んで、2011年にアイルランドで生まれた「CoderDojo」の取り組みを知りました。7歳から17歳までの子どもたちのためのプログラミング道場(以下、道場)をボランティアたちがつくってゆく、国際的な活動です。
「子どもとプログラミングをやれば楽しい」というシンプルなモチベーションとわかりやすいコンセプトに惹かれ、「CoderDojo堺」を2016年2月に立ち上げました。
さっそく、子どもたちの相談役となる「メンター」と呼ばれるスタッフを募ったところ、日ごろ大阪市内の会社にエンジニアとして勤めている人、企業のシステム部門でパートとして働いている人、出産を機にエンジニアの仕事を辞めて主婦になった人などが参加してくれました。
田重田さん 当初は、定員が10名、メンター4、5名くらいの規模から、堺区のコミュニティカフェを拠点に運営していました。
ところが、プログラミング教育が流行っていることや、参加費が無料なこともあってか、募集をかけるとすぐに定員が埋まってしまうようになって。学びたいのに参加できない子どもが出てきてしまったんです。
そこで田重田さんらが解決策として考えたのは、会場を広くしたりメンターの数を増やしたりして、子どもの定員を拡大することでした。
しかし、道場の共通ポリシーを定めた「CoderDojo憲章」に謳われているとおり、道場の運営はあくまでもボランティア主導。これではやがて、メンター役の大人たちが手一杯になり、ボランティアで継続して取り組むのが難しくなってしまいます。
田重田さん それで、一つの道場の規模を大きくするのではなく、泉北のあちこちに小さい道場を増やそうと考えました。そうすれば適度な規模感を保ったまま道場の日程や運営要員を分散できるので、メンターの負担も重くなりませんし、何より子どもたちがどこでも好きな道場に行けるようになります。
そのためにも、まず子どもにプログラミングを教えるサポーターになってくれる大人を泉北で100人見つけようと。
泉北に住みながら大阪市内に働きに出ている人の中には、ITエンジニアの人もたくさんいるはずです。その中で「自分も道場をやりたい」という人が出てきたら、私が道場を開催してモデルを見せ、それぞれの地域にノウハウをシェアする。そうして、置き土産のように道場を開いていくことを目指したのが、今回のプロジェクトです。
子どもだけじゃない、大人だって楽しもう
仕事に加えて、ボランティアで子どもに教えられる人を集めるハードルは、決して低くないはず。メンターとして参加する人のモチベーションはどこにあるのでしょうか。
田重田さん 道場は子どもがプログラミングを学ぶ場ですが、実は同時にITエンジニアのコミュニティ活動とも考えていて。
一般的なITエンジニアのためのコミュニティは、真面目な勉強会のようなもので気軽に参加しづらかったり、そもそも内向きの人が多くて参加する人が限られていたりするんです。
でも、ふだんの仕事で使っているスキルを子どもに教えながら、一緒にプログラミングを楽しむ活動なら、やってみようかなと思う人は多いんじゃないかと。
田重田さんの期待どおり、泉北ニュータウンまちびらき50周年事業のウェブサイトやさまざまな取材記事でプロジェクトの情報を目にした泉北のエンジニアたちが、次々と名乗りを上げてくれました。もともと道場に子どもの保護者として来ていた方で、メンターとして関わってくれるようになった例もあるそうです。
人脈の発掘が生んだ、新しいクリエイティブの生態系
まわりにプログラミングをやっている友達がおらず、親御さんにも教われないという子でも、道場に来れば仲間がたくさんいて、困ったらプロのエンジニアたちが助けてくれる。学ぶ意欲のある子どもたちにとってはまさに理想の環境だと言えるのではないでしょうか。
田重田さん ただプログラミングを学ぶというより、好きなものを自分の手でつくりたい子どもたちが集まって行うクラブ活動のような雰囲気です。
ちなみに、道場に通っている子どもたちは「ニンジャ」と呼ばれているそう。英語圏のエンジニア業界で“Ninja”は「スーパープログラマー」の意味で使われるそうで、そこから用いられている愛称のようです。
そんな毎回の道場で一番盛り上がるのが、その日につくったプログラミングの作品について「ニンジャ」たちに発表してもらう時間なんだとか。
田重田さん 「どんなものをつくったの?」とインタビューしながら、実際にデモして見せてもらうんですが、最初はごく簡単なプログラムしか書けなかった子が、いつの間にか赤外線センサーで制御するラジコンの基盤をつくることができるほどになっていることもあって。
まるで自分の子どものようにその成長ぶりを喜んでいます。
メンター同士で集まると決まって「あのニンジャのあの作品が良かったよね」と盛り上がります。子どもたちの自由な発想から、メンターの大人たちが気づきを得ることも多いです。
道場を巣立った後も、「メンター」の役割を担う若手スタッフである「ユースメンター」として今度は教える側に回ってくれていたり、プログラミングの面白さに魅了され、自主的に制作を続けていたりする子もいるとのこと。
今後の道場のあり方について、田重田さんは「継続性を大切にして、学校ごとのソフトボールクラブのように、地域にとって当たり前の存在にしたい」と話します。泉北の地で発掘した大人たちのスキルと子どもたちの創作意欲が結びつき、ここで新しいクリエイティブの生態系が形づくられていきそうです。

2017年12月3日に。「泉北ニュータウンまちびらき50周年事業」の協賛団体でもあった帝塚山学院大学の会場を使い、通常の10倍の規模で開催された「でかドージョー」。「CoderDojo堺」だけでなく、大阪や奈良、兵庫など近隣の地域で活動する道場が多数参加しました。
何もかも、なりゆきで始まった
次にお話を伺ったのが、「みんなが主役!泉北吉本新喜劇プロジェクト」の実行委員長を務めた野口さん。泉北高速鉄道に勤める現役の車掌さんです。
関西の人なら、劇場や休日のテレビ放送で幼いころから親しんでいる人も多い、吉本新喜劇。泉北も大阪だから…という連想かと思いきや、企画のきっかけは意外なところにありました。
野口さん 実は発案者は僕ではなくて。もともとは、滋賀県の彦根市に吉本新喜劇を招いて、住民参加型の公演を有志で開催してきた知人の一声からスタートしたんです。「彦根でできるなら大阪でもできるやろ」と(笑)
ちょうど僕自身、地域のために何かしたいという思いはありつつ、特に専門的な技術や知識もなく、足を踏み出せずにいるところでした。それで、これを機に何かが生まれるかも、という淡い期待からお手伝いしようと。それが3年ほど前のことですね。
そうして、同じように地域のために活動しようとつながっていた知人たちに声をかけて生まれた集まりから、自然に実行委員会の立ち上げにつながったのだとか。
野口さん なりゆきで実行委員長になったものの、最初は本当にお手伝い程度の気分でした。
そもそも僕は電車の車掌で、どちらかといえば職人のような現場職。会議の議事録の取り方とか、会社を訪問する時の服装とか、名刺の渡し方とか、何も知らず…。「人だけ集めたら、あとはお茶くみでもやっといたらええかな」という感じでした。
それでも、回を重ねるごとに自分より若いメンバーも加わり、相談に乗ることも増えていったそうです。
野口さん きっかけになった彦根の吉本新喜劇では、地元の滋賀大学の学生が運営に参加して、プロから企画やプロデュースの方法を学ぶ試みが行われていました。
だから泉北吉本新喜劇でも、当初から大学と連携したいという思いを持っていて。そんなとき、たまたまある会合で桃山学院大学の先生と知り合い、話を持ちかけました。
泉北だからできることを目指す
頼もしい大学生メンバーと手を組んで野口さんらが目指したこと。それは、泉北だからできる吉本新喜劇の実現でした。
野口さん 泉北に吉本新喜劇を呼んで開催するだけなら、ただの単発的な興行になってしまいます。泉北らしく、今後に続くための工夫をどうするかが課題でした。
そこで「みんなが主役!泉北吉本新喜劇プロジェクト」と名づけ、泉北に暮らす人が一体となって盛り上がる舞台にしようと考えた野口さん。
子どもたちが演者として舞台に上がるようにしたのもその一環です。脚本家の協力のもとで泉北のエピソードを盛り込んだオリジナルストーリーを制作するとともに、新喜劇の役者と共演する子どもたちのオーディションを開催することにしました。
野口さん オーディションには、小学生から中学生までの9学年からだいたいまんべんなく、全部で56名の子どもが参加してくれました。
出演者が多すぎると進行が大変だろうと思って人数を絞るつもりでいたら、脚本の先生のほうから「せっかくなので全員舞台に上げてあげよう」と言ってくれて。いろいろと工夫した台本を練ってくれました。
さらに新喜劇の前座として企画したのが、「泉北お笑い王決定戦」と銘打った、地元住民によるお笑い合戦。地域の中で予選会を開きました。
野口さん 以前から、泉北には漫才のM-1グランプリに参加したコンビがいるとか、とある高校の校長先生が日夜お笑いの稽古に励んでいるとか、そういう噂をいろいろと耳にしていました(笑) なので、きっとうまくいくと。
公演が終わると、運営スタッフとして最後まで走り切った大学生のメンバーの中には、「これで終わってしまう。新喜劇ロスだ」と泣き出す子もいたそう。「そうした成長を見ることができたのは嬉しかったですね」と野口さんは目を細めます。
環境のやりくりが、自分を楽にする
ところで田重田さんと野口さん、それぞれエンジニアと車掌という肩書きを持つ中で、プロジェクトとの両立は大変ではなかったのでしょうか。
田重田さん 独立したばかりだったということもあり、とても大変で、正直なところ食べていくための仕事にも支障が出ました(笑)
ただそれでも、道場は定期的に開催するための枠組みが決まっていたので、なるべく毎回の準備や運営をルーティン化して自分の負担を減らそうと。「イベント疲れ」をしてしまわないように気をつけました。
野口さん 以前から、「運転士だから、車掌だからと言って、電車を動かして止めるだけでいいのか? 鉄道と周辺地域は共存共栄の関係なのだから、鉄道会社の社員として地域の活動をすることも大切なのではないか」と考えていました。
だからこのプロジェクトはもちろん、地域のための活動であれば何でも鉄道の仕事の延長という意識を持っていて。メディアに取り上げてもらうときにも、自分が泉北高速鉄道の車掌だということを堂々と押し出しました。
その甲斐あって、社内の人も「野口君、こんな活動してるんや」と応援してくれるようになって。ある日出勤したら、活動が掲載された新聞記事がでかでかと掲示されていたこともありましたね(笑)
時間のやりくりは確かに大変で、ずいぶん有給休暇を消費しましたが、上司や同僚が「泉北のあれか、頑張ってや」と声をかけてくれる環境だったので、取得もしやすかったです。
心に残る体験が豊富なら、いつか戻ってきたいまちになる
お二人のお話を聞き、それぞれのプロジェクトの活動を当初から見守ってこられた中川さんはこう語ります。
中川さん 異なる動機から始まったとはいえ、どちらのプロジェクトも、「子ども」にフォーカスした点が共通していました。
子どもを育てるという目線でまちを見たとき、泉北の場合は豊かな自然があります。ただ一方で、いわゆる都会にあるようなハイエンドな文化機能は少なく、そうした経験は得づらいですよね。
そんなまちに暮らす子どもたちの前で開かれた、プログラミングが学べる道場や、あの吉本新喜劇の公演。これらの経験はきっと、子どもたちが夢を育むきっかけになったのではないでしょうか。
ニュータウンのこれからを考えたときに大切なのは、子どもたちが成長し、進学などの理由で仮に地域を出ていったとしても、また戻ってきたいと思ってもらえるかどうか。そのためには、自分の心に響く体験ができるコンテンツを、子どもたち自身がたくさん見つけられるようなまちでなければならないでしょう。お二人はそれぞれ、そのひとつをつくられたのだと思います。
大阪市の中心部まで電車で1時間弱と都市部へのアクセスに優れる泉北ニュータウンですが、ほかのさまざまなまちと同様に、ただそこで暮らしているだけで得られる経験には限りがあることもまた事実。行動範囲の限られる子どもたちにとってはなおさらです。
そんな彼・彼女たちにとって、プロのエンジニアとものづくりの面白さを共有することや、プロの役者と芝居をつくりあげることは、中川さんの言葉のとおり、きっとまだ見ぬ自分の将来像を刺激する体験になったことでしょう。
今日・明日の話ではないかもしれませんが、彼・彼女らのアイデアが、将来のニュータウンやそこで暮らす人々の生活を大きく変えるかもしれません。
中川さん ニュータウンそのものだけではなく、近隣の農村も含めた周辺環境を全体的にどう魅力的にしてゆくか。田重田さんや野口さんのように、一緒に考えてくれる地域のプレイヤーがもっと増えるといいですね。
まちの明日を担う子どもたちの世界を広げるコンテンツを、自分が暮らすまちにつくりだすために必要なこと。今回ご紹介したお二人の取り組みから学べるポイントは二つあります。
まずは、自分のまちに眠る多様なネットワークの潜在力を信じ、発掘すること。そしてそれを活かし、あくまでも自分自身が楽しめる動機を見失わずにプロジェクトを進めてゆくことです。
みなさんも、自分のまちが秘める人のポテンシャルを探ることから始めてみませんか。そこで仲間との人脈を掘り当てたら、自分たちの意欲が向かう限り、チャレンジを続けてみてください。新しい世界の広がりに心を躍らせる次の世代が、きっとその後ろ姿を見ているはずです。
(写真: 寺内尉士)