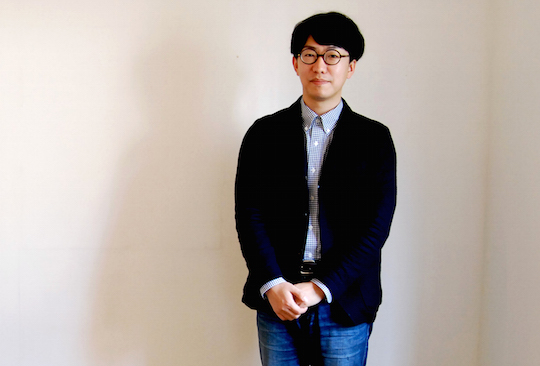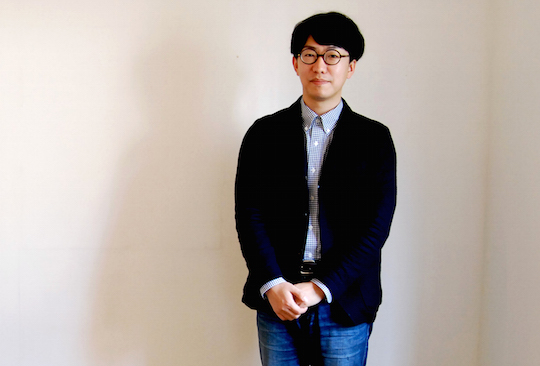
丸眼鏡の奥に映る優しい眼差しと少しハイトーンの穏やかな声が印象的
絵を描くこと、手紙を書くこと、料理をつくること、音楽を奏でることetc…ツールはさまざまに、誰かを想って行うそんな表現の先には、「その人の笑顔が見たい、幸せになってもらいたい」という目的があるもの。
今回、紹介する福岡市在住のデザイナー、中川たくまさんは、「デザインという表現ツールを使って、身近なところから社会的な問題を解決したい」との想いから、イラストレーターで洋裁も行う奥さまのなつきさんとともに、2007年から「青い月」として活動を始めました。
プランナー/デザイナー/レタープレスプリンター
1978年福岡市生まれ。2007年にデザイン事務所「青い月」を開始。主に福祉・病院・子ども・NPO・文化芸術などの分野で、プランニングとコミュニケーション・デザインを行う。2009年に博多の活版職人から道具と技術を受け継ぎ、活版印刷を始める。2011年に活版発祥の地、長崎で「活版巡礼展」を企画・開催。以降、活版印刷を未来につなげる活動に力を入れている。2015年、社会的包摂に特化したデザイン活動「ポランズ」を開始。http://aoi-tsuki.com
今、ご覧になっている「マイプロSHOWCASE福岡編」のトップページのデザインや、グリーンズでも紹介した「SOS子どもの村」のロゴデザインなど、行政から美術館、NPOまでたくさんの人の想いをかたちにしてきた中川さん。

中川さんがデザインした「SOS子どもの村」のロゴ

フォトラボスタジオ「アルバス」のロゴ
仕事的には大きな成果を得てきたプロフェッショナルに思えますが、話の端々で出てくるのは「私はとりたててデザインが上手なわけでも、ビジネスが好きなわけでもないんですよ」という言葉。やわらかな物腰とは真逆のきっぱりした物言いに、優しさだけでない、芯の強さや覚悟を感じます。
では、中川さんが大切にしたいこととは何なのでしょう。プランナー、デザイナー、そして時に、プライベートプレス(活版)のプリンターとして。それらの表現をかたちづくった根底には、子どもの頃の原体験がありました。
長崎で過ごした幼少期
中川さんは福岡市出身ですが、小さい頃は長崎市内の祖父の家で過ごしていました。そこで暮らした思い出や記憶が、中川さんの生き方に大きく影響し、つながっているといいます。
海と山に囲まれた、限界集落といわれるような里山での暮らし。土の香りを感じ、コバルトブルーの海の表情が刻々と変わる様を眺めて過ごし、自然と人とのつながり、孤独感も本能的に肌身で感じた幼少期でした。

祖父とよく一緒に見た風景
小さい頃から絵を描くのは好きだったみたいで、魚の絵を書いたりしていたのを、祖父がずっと飾っていてくれて嬉しかったのを覚えています。長崎という土地柄、戦争や原爆の話も聞いていました。幼心に怖かったですね。
その後、福岡に戻って10代後半の頃、中川さんがデザインの道を意識するきっかけとなったのが、アルバイトを始めたアジア料理店でした。
お店では、絵が好きだということで、メニューを書いたり、壁に絵を描いていたりしていたんです。お客さんからも反応があったりして、なんとなくそういう方面に進めたらいいなとは思っていました。
お店にはタイ人のコックがいて、バックパッカーが立ち寄るようなところ。当時はまだインターネットも発達していない時代に、さまざまな人から自然と影響を受け、10代でひとり旅に出ようと思い立ちます。
中川さんがリュックを背負って旅に向かった先は、軍事政権下にあった仏教国のビルマ(ミャンマー)でした。
見るものすべてに圧倒され、惹き付けられる自分の知らない世界。現地で知り合い、案内してくれた地元男性との出会いに、勇気づけられたそう。
あるとき、彼が木彫りの人形をプレゼントしてくれて、「君も希望を持てるようなことができるよ」って、思ってもみなかったことを言ってくれたんです。
というのも、民主化を求めて闘うアウンサン・スーチーさんの存在を、そこにいるみんなが「希望」だと言うんですね。心が震えました。路上生活者もいっぱいいる貧しい国だけれど、あきらめていない。あきらめたらおしまいだと、みんな解っている。
そこで、自分の中にあった閉塞感が和らいで、「希望を持てるようなことがしたい」という気持ちを持てたんです。

Some rights reserved by Chatham House, London
人の役に立ちたいと、デザインの道へ
帰国後、伝染病に罹って入院したことも、今では笑って話せる思い出。体調が回復して、デザインの仕事を探し始めたものの、経験が必要な職業。時間はかかりましたが、ある時、これはという求人情報を目にします。
「経験問わず、人の役に立てる仕事」ということが募集内容に書いてあって。ただ、条件がイラストレーターを使えることだったんですね。基本、楽天家なのでどうにかなるだろうと思って「できます」って言って(笑)
そこでは、点字の印刷やバリアフリーのマークをつくっていました。習うより慣れろでイラストレーターも1週間くらいで覚えました。
色も文字のことも知らなかったものの、枠にとらわれることなく独学でデザインを学べてよかったと振り返る中川さん。次の会社では、いよいよデザイナーとして就職することに。
その会社ではデザイナーも営業する必要があり、九州地域の官公庁への企画提案をよくしていました。今でこそ地域ブランドへの働きかけが盛んになっていますが、村祭りに参加して視察したり。
いろんな町と人の営みを知ることができたことも、経験として面白かったですね。
そのときに自身が飛び込みで営業したのが、少年自然科学文化会館や福岡県立美術館など。中川さんらしい純粋なアプローチが、双方の担当者の胸に響きます。
少年自然科学文化会館へは、「星が好きな子どもたちが増えたら、戦争はきっとなくなる」というような想いをラブレターに綴って、リーフレットを勝手につくって持って行ったんです。そこでは、ロゴマークなどをつくらせてもらいました。
福岡県立美術館にも「アートを本当に必要とする人たちのもとに届けたいんです」とお話しして企画を出しました。そうしたら、担当の方ががんばって通してくださって。それ以降、数年に渡って展覧会スケジュールのパンフレットを制作させていただきました。

福岡県立美術館のパンフレット
中川さんのこうした姿勢が人の心を掴む理由。それは、仕事としてのつながりや枠を超え、いつのときも相手と正直に向き合い、心を通わせることを前提にしているからだと、はっとさせられます。
美術館の担当の方とは、それ以来の付き合いなんですが、メガネの選び方や職人が作る靴を履くこと、お昼にそば屋でお酒を愉しむことなど、たしなみを教えてもらいました。そんな粋なことを20代半ばで教えてもらって、デザインの輪郭をそのときに学ばせてもらった気がします。
フリーへの転身と活版との巡り合い
信念を持って心のまま、導かれるように生きてきた中川さん。27歳の時、「デザインをもっと必要している人のところへ」という気持ちが強まり、独立を決めます。「青い月」という屋号は、パートナーのなつきさんが名付けたもの。
水面に映る姿や、凪いだ海に沈んでいく月の美しさが私も妻も好きで…弱さや未熟な感じもありますよね。後で調べてみたら、「満月がひと月に2回訪れる現象をブルームーンと呼ぶことがわかって、めったにない幸せなことという意味もあったりするんですね。
デザインって枠にはめてしまいがちになんですけど、ありふれていないもの、その人が求めているものをかたちにしたいという気持ちにしっくりきました。
活版印刷の道具と技術を引き継いだのも、ちょうどその頃。きっかけは、フリーになる以前から足繁く通っていた活版所の主からの依頼でした。
ある日、めったにない電話がかかってきて。辞めようかどうしようかという相談でした。その瞬間、私に譲ることを決めてかけてきてくれたんだなって解ったんですね。
そのとき、自分を勘定に入れないで、相手の気持ちを受け入れることが自分の道なんだろうなと感じたんです。
覚悟を決めて、3ヶ月という短い修行期間を乗り越え、活版の技術とともに印刷機と活字を受け継いだ中川さん。「デザインや活版印刷をコミュニケーションツールとして活かせる場をつくりたい」と、東区箱崎の古民家にアトリエを構えます。

物語のあるブックジャケット。宮沢賢治の「ポラーノの広場」の一節を引用
その後、活版の歴史や文化を知るための旅へ出ようとルーツを調べたところ、それは故郷の長崎にありました。
必然というか、いつか祖父と過ごした長崎へ恩返ししたいという漠然とあった気持ちに呼ばれたのかもしれません。
それを機に、長崎県美術館で「長崎活版巡礼展」を実現した後、活版印刷の魅力を再発見してもらい、「あるべき場所に在り続けてほしい」と、教育委員会などの行政へ活版文化の保存を呼びかけてきました。
その働きかけもあって、今年の9月には長崎県全体で「長崎活版巡礼祭」を開催できることになったそうです。

「長崎活版巡礼展」の様子
自分を勘定に入れずに生きること
そんな中川さんにまたひとつ、大きな転機が訪れたのは、2011年5月のこと。自転車に乗っていて事故に遭います。
活版は親指、人差し指で活字を拾うんですけど、利き手に障害が残ってしまって、物理的な理由で続けられなくなったんです。これは、いよいよ活版を自分のためでなく、他者のため、未来に残すために尽力しなさいというメッセージなのかなって妻とも話し合いました。
人生って面白いなぁと思うんです。困難というか、うまい具合に楽をしないようになっていて、その分ありがたみを深く味わえるというか(笑)
そう、あっけらかんと言いのける中川さん。アトリエを閉じてからも、子ども、福祉、障がい、刑を終えた人が社会復帰できる取り組みに携わり、自分ができることを前向きに積み重ねていきます。
そんな中川さんのもとには、自ずと重たい案件がやってくることもしばしばです。
本当にデザインを求めているところは、お金のないところも多いんですよね。お金が発生したのが3年後くらいのところもありました。
でも、それを私の仕事の判断基準にはしたくないし、デザインしたから終わりではなく、その後のつながりも大事にしたいんです。
「その代わりに、いろんな社会課題を学べるといういい部分もある」と中川さん。だからこそ、デザインしたものではなくて、デザインから広がる可能性を信じることを大切にしています。

ここで、中川さんの最近の仕事をいくつかみてみましょう。例えば、震災復興に関連して、岩手県・陸前高田の案件を手がけました。
西村佳哲さんが相応しいデザイナーを探していて、パートナーのたりほさんが「中川くんがいいんじゃない」と声をかけて下さいました。
ただ、被災地との距離がある分、バイアスがかかっていて、時間的なものもあってそこに寄り添えるのかという迷いがありました。
依頼された内容は、復興に向かうために造られる宿泊・滞在施設のロゴデザインを作ること。情報量が全くないなかで解像度を上げていくという大変な作業でした。
言葉が出ない風景を目にしつつも、ヒアリングを重ねて、ワードを出して、デザインへと落とし込んでいきました。
素直な気持ちを会議のテーブルを離れた時に聞くこともできました。結果、3案つくって持っていったもので、私が陸前高田で最初に見た海の景色をデザインしたものが通りました。
修正がなかったのは、気持ちが少しだけでも寄り添えたからかなと思います。
問題を可視化して希望をつなぐことが使命
そして、中川さんが特に強い思いで望んでいるのが「子ども」というテーマです。昨年、第一子が誕生し、さらにその存在が愛おしくなったと同時に、重大な課題だと思うようになったといいます。
我が子をこの手に抱いた時に、この子の後ろにたくさんの子どもたちがいるんだなって実感したんです。実際、子どもの貧困や養護の問題は、福岡でも社会的な課題になっていて。
重たく切実な声を受け止めることって、やっぱり苦しいんです。でも当事者に比べたら、ぜんぜんですよね。「誰のためのものか」。今の事業の多くは、当事者が見えずに表層で語られることがあまりにも多くて。
おかしいことはおかしいと言える社会であってほしいなって思うんですよ。
そうした想いを重ねてきた今、中川さんが向き合っているのが社会的包摂(ソーシャルインクルージョン)のデザインです。
「ポランズ」という活動名を付けて、ふくおかNPOセンターの人たちと一緒に生きづらさを抱える人たちのための居場所づくりや、社会的課題をもっと柔らかく、わかりやすく可視化していくことに取り組んでいます。

ふくおかNPOセンター代表の古賀さんと。社会的課題やそれに取り組んでいる人たちを紹介するフリーペーパーを発行予定

点字新聞を再利用した“見えない”クリアホルダー「un-clear folder」
たくさんの石が転がっている道を歩きやすくするために、その石を取り除くことがデザインの役割で、その石が大きければ誰かに手伝ってもらえばいい。
完全に舗装された道よりも、道を歩く感覚はあったほうがいいですよね。それを障害と思わずに長いスタンスでやっていければと思います。
こうと思ったら信じる道を一直線の中川さんだから、行政や発注者と「ケンカしちゃう」ことも多々あると笑いますが、これまでデザインして嬉しかったのは、同じ風景を見て、対話を重ね、結果かたちになったものを見た瞬間、「あなたがいてくれて、よかった」というひと言。その言葉に救われ、自分の存在価値を感じるといいます。
ひとりでも多くの人が自分の人生を愛せるようになればいいなと思うんですよ。みんな自分たちがこうありたい、こう暮らしたいと思って日々を過ごしますよね。
けれど、同じ線上には誰かがいて、そして自分がいるということに思いを馳せることが大事じゃないのかなって。
私たちは、草の根の話でなく、切り花の話をしていると感じることが多いんです。その時々はきれいだけれど、やがて枯れてしまう。根っこに水やりをして、ちゃんと育てれば、ずっとずっと次の世代まで咲き続けることができるのに。
草の根でふんばっている人たちとつながっていくこと、見ているつもりでも見落としていることがあって、そこに目を向けて掬い上げていくことが私の役割なんじゃないかなと思っています。
日々の中で、よりよい方向へ変化を生む可能性を信じ、伝えるべき大切な想いを素直に相手に表現すること。
そして、大きな問題でなくても、兄弟や友人、周りの誰かの悩みを聞いてみたり痛みを分かち合うことができていけば、私たちも中川さんのように、そこから何か始まるもの、希望の光を見いだせるのかもしれません。