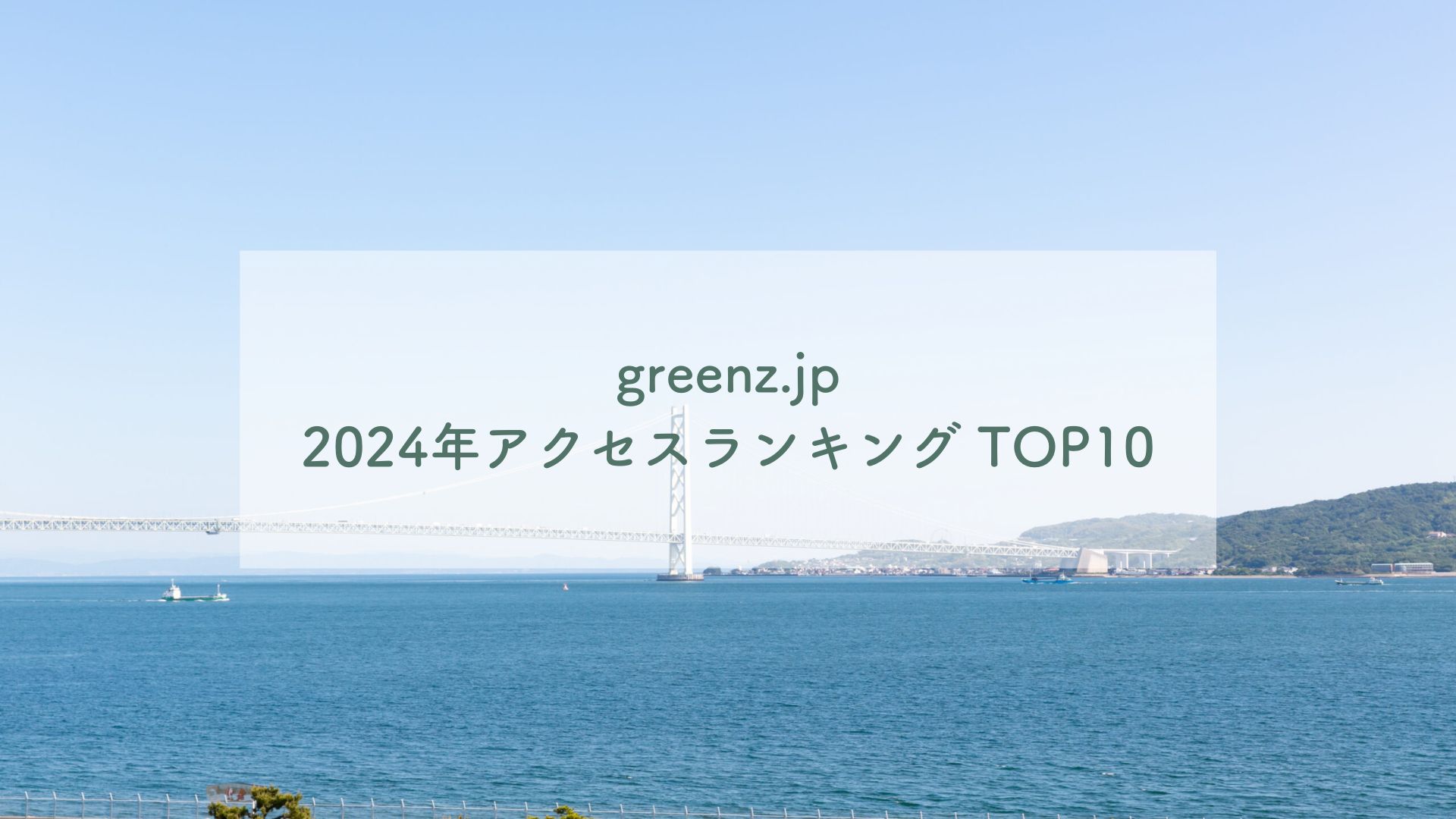2025年が明けました。
いつもgreenz.jpをご愛読いただきありがとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
能登半島沖地震から1年が経過しました。グリーンズではボランティアやタブロイド誌『グリーンズ号外』の制作というかたちで現地の様子を届けてきましたが、今年も能登の方々に心を寄せ続けていきたいと思っています。あらためて一日も早く平穏に復することを、心よりお祈り申し上げます。
新年1本目となる本記事では、2024年に多くの方に読まれた記事や、グリーンズの現在地を示す記事を振り返りたいと思います。
タブロイド誌『グリーンズ号外 vol.01 能登半島のいま』を置いてくださる方を募集しています。詳細は「編集長・増村江利子が『グリーンズ号外』で伝えたい、能登半島のいま。ゆっくりでも前に進む能登が、私たちの未来に教えてくれること」をご覧ください。
2024年アクセスランキング TOP10!
まずは2024年に公開した新作記事152本のなかから、アクセス数の多かった10本をご紹介します。環境再生に向けた全国各地の取り組みから、お金の概念を変えるソーシャルデザイン、社会をよくする海外のアイデアまで、幅広い記事がランクインしました。

きれいになりすぎた“貧栄養”の瀬戸内海に、生物多様性を取り戻す。兵庫県の漁師たちが陸へはたらきかけ、海に栄養を注ぐ 「豊かな海づくり」 (村崎 恭子/Regenerative Design)
目の前に広がる青い海。明石海峡大橋の向こう岸は、淡路島。思わず「きれいだなぁ!」と、波の音に逆らうように感嘆の声を出してしまいます。「本当はもうちょっと緑色の方が“豊かな海”なんです」と教えてくれたのは、兵庫県漁業協同組合連合会の樋口和宏さん。実は今、瀬戸内海、とりわけ兵庫県の海では漁獲量が著しく減り続けており、多くの漁師さんの頭を悩ませています。そしてその原因は、この海の青さにあるというのです。

新聞紙を提げて出かけよう!「折って、のりづけ」だけ、簡単なのに強度あり。新聞エコバッグのつくり方 (藤野 あずさ/いかしあうつながりのレシピ)
お土産用の袋としておなじみになってきた「新聞バッグ」を、自分でもつくってみませんか? 手提げ袋として使うのはもちろん、庭で咲いた草花や採れすぎた野菜を入れてご近所さんにおすそ分けしたり、旅先で入手した新聞やフリーペーパーでつくってお土産を入れたり。つくった側も、もらった側も、ちょっとうれしくなりますよね。

「耕さない農業」は、私たちの食の未来を変える。『ミミズの農業改革』著者・金子信博さんに聞く、不耕起草生栽培のすべて (岩井 美咲/Regenerative Design)
『ミミズの農業改革』の著者・金子信博さんが実践研究している「不耕起草生栽培」は、土壌の劣化を防ぐだけでなく、農業従事者の営農コストを下げて収益を上げ、さらには、作物の味を向上させることにもつながります。いいこと尽くしのように感じるこの栽培方法は、なぜ日本で普及していないのでしょうか。詳しくお話を伺うため、私たちは福島大学の金子さんの研究室を訪れました。

オレはシャベルで革命を起こす。ロサンゼルス発、食の砂漠をゲリラ畑へと美しく再生した“ギャングスタ” (片岡 麻衣子/Regenerative Design)
農具を持ったこの男性は、自らを「ギャングスタ・ガーデナー」と呼び、地域で革命を起こしている、Ron Finleyさん。治安の悪いことで知られるアメリカ・ロサンゼルスのサウス・セントラル地区で、「なんでもいいから植えろ!(Plant some shit!)」を合言葉に、10年以上前から、ゲリラ的に街の中に菜園をつくり、食べられる作物を植える活動に取り組んでいます。そのきっかけは、近所で新鮮なトマトが手に入らなかったこと。

これぞ、「人生100年時代」の性教育。ガーデニング用品売り場で始まった、シニア世代の性感染症を防ぐユーモラスなキャンペーン (片岡 麻衣子/greenz challengers community works)
性行為にまつわるテーマは、どの世代でもオープンに話しづらいもの。そこで考え出されたのが、ガーデニングをフックにしたキャンペーンです。“寝室にいないときは庭にいるはず”ということで、各地のガーデニング用品売り場で、野菜や果物の種の袋を装ったパッケージにコンドームを入れ配布することにしたのです。
6~10位はこちら
奪い合う経済から、分かち合う経済へ。非営利株式会社eumo代表・武井浩三さんに聞く、共感資本社会における経営論
(佐藤 史紹/supported by greenz people)
瀬戸内の小さな島からオーストラリアへ、そしてまた島へ。島暮らしの豊かさを世界に伝える宿「とくと 豊島」をかたちづくる、大きな家族
(佐藤 有美/supported by greenz people)
日焼けや虫刺されにも。古来の薬草・ヨモギを摘んで万能ヨモギオイルのつくり方
(やなぎさわ まどか/いかしあうつながりのレシピ)
棚田の再生から“新しい共同体”をめざす。岡山県美作市の集落 「上山」にみる、現代版里山暮らしのあり方
(甲斐 かおり/sponsored by NPO法人英田上山棚田団)
何度も読みたい、足元の暮らしを見直す過去記事3選
greenz.jpには、季節の節目に、人生の転換期に、何度でも読み返していただいている、息の長い記事が多くあります。なかでも、2024年も多くの方に読んでいただいた過去記事TOP3を紹介します。

20秒でゴミ袋に。脱プラスチックの新しい生活様式は「読んだら折る」。新聞ゴミ袋のつくり方
(やなぎさわ まどか/いかしあうつながりのレシピ)

草刈りしちゃうその前に。ドクダミを活かす「虫除けスプレー」のつくり方
(やなぎさわ まどか/いかしあうつながりのレシピ)

92歳で亡くなるまで70年間、自立と自然を大事に生きたターシャ・テューダー。彼女がその暮らしを貫いた理由は「好きだから」
(石村 研二/グリーンズの本棚 ©2017 映画「ターシャ・テューダー」製作委員会)
2025年春に書籍化!グリーンズが考える「リジェネラティブデザイン」
2023年から探究を続けている「リジェネラティブデザイン」が、2025年、いよいよ書籍になります! グリーンズが考える「リジェネラティブデザイン」とは、自然環境の再生と同時に、社会と私たち自身もすこやかさを取り戻す仕組みをつくること。自然へのまなざしから、暮らしやビジネスへの接続まで、ぜひ読んでいただきたい「リジェネラティブデザイン」の記事をご紹介します。

「内なる自然」の声を聴け。坂田昌子さんに学ぶ、自然に対する倫理観と環境問題への向き合い方 (やなぎさわ まどか/Regenerative Design)
スキー場拡張やショッピングモール建設のために、切り倒される木々。そのニュースに憤りを感じつつも、どこか無力さも感じてしまう…。この憤りの感情は「内なる自然によるもの」だと教えてくれたのが、坂田昌子さんです。生物多様性の大切さを伝える彼女のお話は、私たちの心に眠る自然への感覚を呼び覚ましてくれます。失いつつある大切なものに、どう向き合うべきか──坂田さんにお訊きしたく、高尾の山を訪ねました。

アイスクリームから、経済も生き方も再定義する。神奈川県茅ヶ崎市の不耕起栽培農家「はちいち農園」衣川木綿さん・晃さんが、「SOYSCREAM!!!」を立ち上げた理由 (池田 美砂子/Regenerative Design)
神奈川県茅ヶ崎市で、妻の木綿さんとともに不耕起栽培による環境再生型有機農園「八一農園」を営む衣川晃さん。ミュージシャンの世界からファーマーに転身し、さらには地球温暖化の緩和策として不耕起栽培による土壌再生面積の拡大を目的としたアイスクリームブランド「SOYSCREAM!!!」を立ち上げ、不耕起栽培農家を支援するビジネスモデルを構築しています。

旅を入り口に、里山の知恵を世界へつなげていく。京都・京北の「ROOTS」が“リジェネラティブツーリズム”を通じてデザインする多様な関係性 (村崎 恭子/Regenerative Design)
「茅葺屋根の家に住んだら、自分自身が自然循環の一部になっていると、すごく感じるようになりました」。自身の変化をそう語るのは、京都・京北に15年前に移住した曽緋蘭さん。2018年、同じく移住者である中山慶さんとともに「ROOTS」を創業し、京北で“里山の知恵”を肌で感じられるツーリズムを展開しながら、世界中の人たちにその知恵を継承することを探究しています。
私たちは何を耕し、実践していくのか
greenz.jpを運営するNPOグリーンズでは、記事というかたちだけでなく、部署の垣根を越えたさまざまなプロジェクトに取り組みながら、「生きる、を耕す。」を探究しています。そんなグリーンズの現在地をお届けする記事を紹介します。

合言葉を「生きる、を耕す。」にリニューアルしてから、私たちは何を耕し、実践してきたのか?【NPOグリーンズ13期活動報告】
第13期(2023年12月〜2024年6月)にgreenz.jpが「実践するWEBマガジン」として、どのようなプロジェクトに取り組み、探究と実践を重ねてきたのか。共同代表・植原正太郎と編集長・増村江利子が振り返り、14期への意気込みとともに語りました。

ポスト資本主義の転職サービスをつくる。グリーンズが求人サイト「WORK for GOOD」に込めた思い
2024年5月に公開した、「働く」で社会を変える求人サイト「WORK for GOOD」。日本や世界のソーシャルビジネスを取材しながら培ってきたグリーンズのネットワークや編集力をいかして「やりがいのある仕事」を紹介していきます。「WORK for GOOD」をはじめる背景にある思いを、NPOグリーンズ共同代表・植原正太郎が語ります。
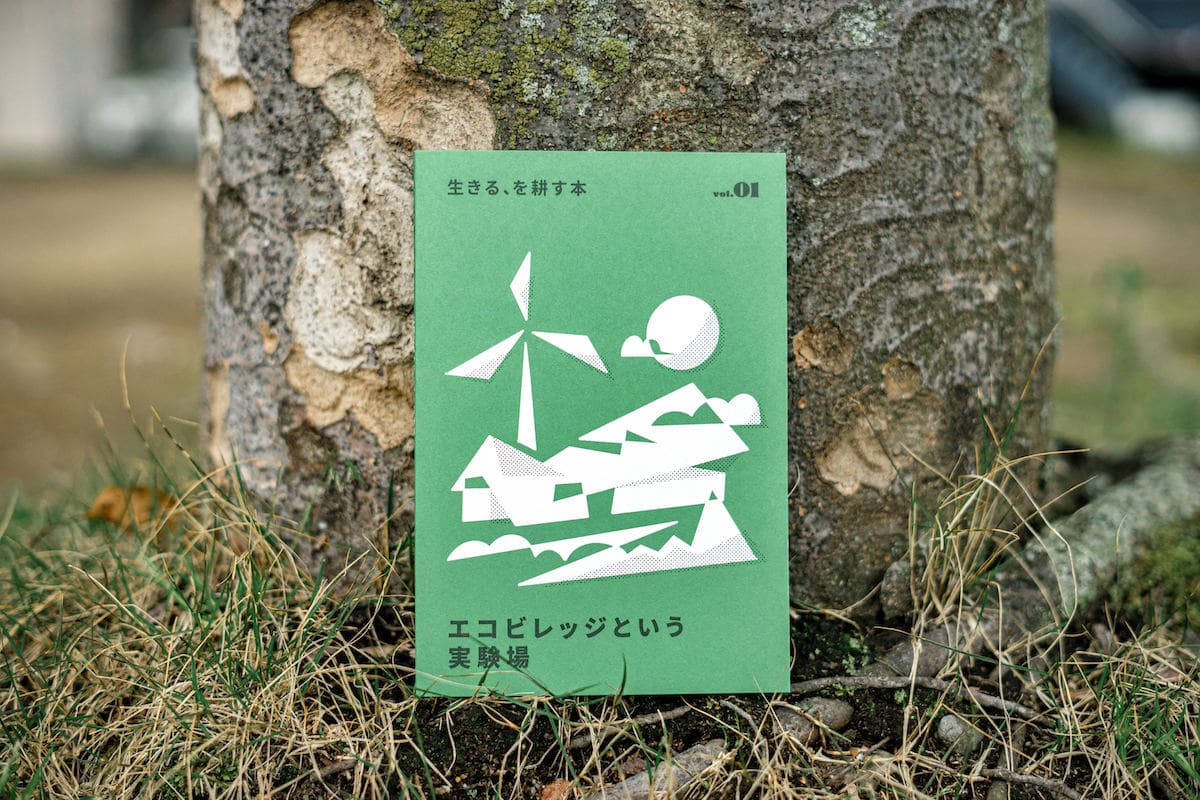
greenz people限定『生きる、を耕す本』が完成!さまざまな社会実験を探求するシリーズ本vol.01「エコビレッジという実験場」の全貌を紹介
WEBマガジン「greenz.jp」のメディア運営を寄付で支えてくださっている読者のみなさん「greenz people」だけにお届けしてきた特典本を、2024年にリニューアル。『生きる、を耕す本』として、第1号は「エコビレッジ」をテーマにお届けしました。ただいま新規入会いただいた方には第1号をお届けするとともに、2025年春には第2号を発行します!
“貧栄養”の海の生物多様性とは、耕さない農業とは、分かち合う経済とは何か。
2024年のヒット記事からは、読者のみなさんがグリーンズと一緒に探求をしてくれている姿が見えてきました。
今年もさらに気づきの多い記事を届けていくとともに、書籍『リジェネラティブデザイン』の出版や、「リジェネラティブ デザイン カレッジ第二期」の開講、グリーンズの寄付読者向け限定本『生きる、を耕す本vol.2』の発行など、WEBマガジン「greez.jp」は、2025年も「生きる、を耕す。」を実践するメディアであり続けます!